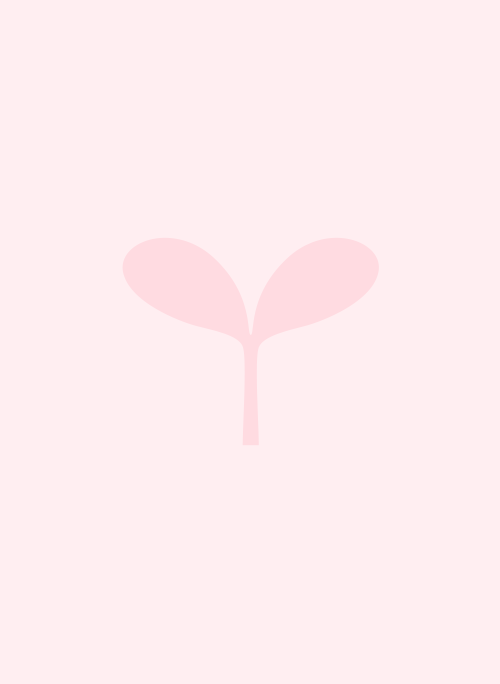「本当はこんな手荒なことはしたくないんだけど、君がいけないんだよ」
ふわりと頬を撫でられて、ユーリは悲鳴を飲み込んだ。
優しい声。
優しいまなざし。
でも、全て、にせものだ。
ひやりとした地下室のベッドに横たられ、手も足も拘束されて、動きがとれない。
青年の背後の壁にびっしりと並んだ蝶の標本に、羽ばたきをやめた羽を彩る鱗粉の輝きに、どうしても目が行ってしまう。
ふわりと頬を撫でられて、ユーリは悲鳴を飲み込んだ。
優しい声。
優しいまなざし。
でも、全て、にせものだ。
ひやりとした地下室のベッドに横たられ、手も足も拘束されて、動きがとれない。
青年の背後の壁にびっしりと並んだ蝶の標本に、羽ばたきをやめた羽を彩る鱗粉の輝きに、どうしても目が行ってしまう。