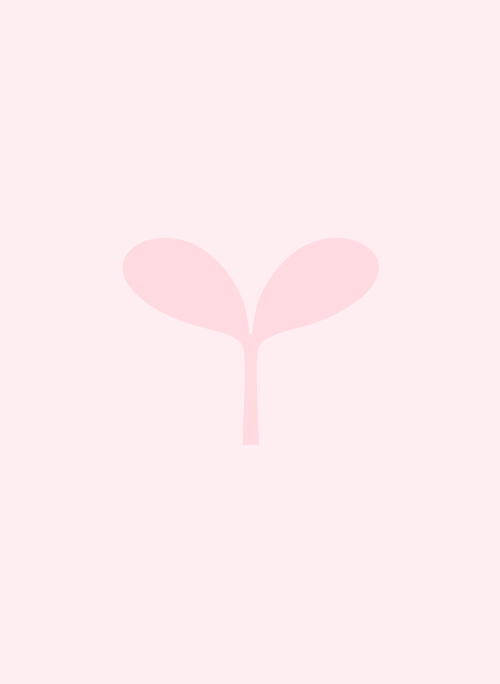「あのね、
言いづらいかもしれないけど
聞いてもいいかな?」
「なんですか?」
「なんで家を急に飛び出してきたの?」
お茶を一口飲んで話しを切り出す優里。
「お母さんを見た時はいつもと変わらなくて
安心したんだけど・・でも、
別人だってすぐわかった。
家にね、知らない男の人がいたから。
それに、私に気づいたお母さんがね
”あら帰ってきたの?不良娘”って言ったの」
空白の時間が流れた。
ユリツキは息が止まりかけた。
「私がなんのこと?って
聞いてもお母さん無視してて、
その男の人と楽しそうに話していて・・・
そして、男の人に向かって言うの
”この子が私の亭主をころしかけた”って」
聞かなければ良かったとユリツキは後悔した。
大島優里は背筋を伸ばし話を続ける。
「それで私、お母さんに言い寄ったの、
何で?て、そしたらね男の人が
”お前は自分の親父に襲われて、
反抗して、逆に殺そうとしたんだろうが!
親の言うこと、することに、
子供は黙って従うんだよ、憶えてろ!って」
「でもそれはこの世界の君で。
君がやったことでは」
なんの慰めにもならない言葉と知っていた。
今朝までは優しい声で
語りかけてきた母親の声色。
若い男にすがるどろどろとした砂糖水のような
甘ったるい汚辱の言葉。
尊敬する父を慕うはずの母親の細い腕が、
知らぬ男の腕に絡む姿。
言いづらいかもしれないけど
聞いてもいいかな?」
「なんですか?」
「なんで家を急に飛び出してきたの?」
お茶を一口飲んで話しを切り出す優里。
「お母さんを見た時はいつもと変わらなくて
安心したんだけど・・でも、
別人だってすぐわかった。
家にね、知らない男の人がいたから。
それに、私に気づいたお母さんがね
”あら帰ってきたの?不良娘”って言ったの」
空白の時間が流れた。
ユリツキは息が止まりかけた。
「私がなんのこと?って
聞いてもお母さん無視してて、
その男の人と楽しそうに話していて・・・
そして、男の人に向かって言うの
”この子が私の亭主をころしかけた”って」
聞かなければ良かったとユリツキは後悔した。
大島優里は背筋を伸ばし話を続ける。
「それで私、お母さんに言い寄ったの、
何で?て、そしたらね男の人が
”お前は自分の親父に襲われて、
反抗して、逆に殺そうとしたんだろうが!
親の言うこと、することに、
子供は黙って従うんだよ、憶えてろ!って」
「でもそれはこの世界の君で。
君がやったことでは」
なんの慰めにもならない言葉と知っていた。
今朝までは優しい声で
語りかけてきた母親の声色。
若い男にすがるどろどろとした砂糖水のような
甘ったるい汚辱の言葉。
尊敬する父を慕うはずの母親の細い腕が、
知らぬ男の腕に絡む姿。