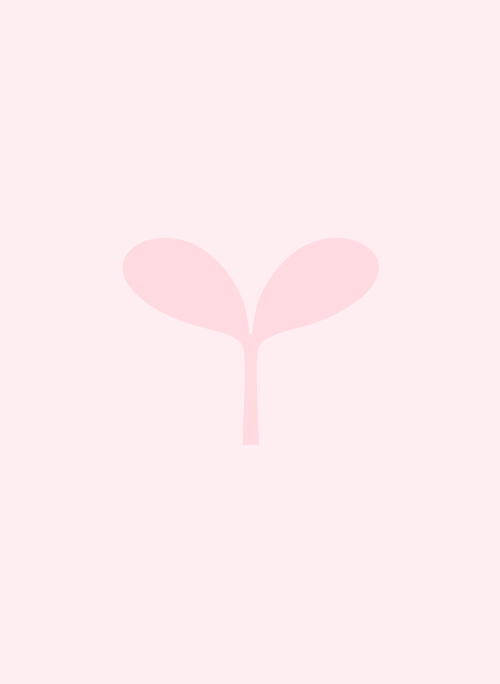「やっぱり、信じられないな・・
私なんかが・・」
「自分からなりたいって決心して、
今日、あの事務所訪ねたんでしょ?」
「うん、でも軽い気持ちだったし、
私より可愛い人沢山いるから、
ちょっとだけテレビに出れたら、
それでいいかなって気持ちだもん」
1週間前、
あの女社長にスカウトされた大島優里は
今日の朝方まで苦悩していた。
事務所に顔だすか、出さないかと。
芸能界に興味があったのは事実らしい。
「う~ん、今は確かに実力派女優にはほど遠いかな。
ぼくは君の将来を知っているから、
こんなにドキドキするけど、
知らない人が見たら
多分普通の女の子かな?ん?
上の中くらいかな?」
「やっぱり自信なくした」
ふて腐れたように口を尖らせる優里。
「ごめんごめん、
気のもちようで変わっていたんじゃないのかな。
チャンスがあって、
周りの人たちが大島さんを好きになって。
それで期待に答えようと努力して、
がんばろーって思って
眠っていたモノが引き立ってきてさ、
それで人気がでてきたんじゃないかな?」
ユリツキはこの時、
始めて自分の話し方、
考え方に微かな、
はっきりしない重石のような違和感を感じた。
”不器用”と、いった、
清潔な言葉では片付けられない
どこか不潔な物だった。
「そうなのかな~」優里は、
しんみりとした声で頭を傾け言った。
「フォローになってません?」
「う~ん。どうかな」
「でも、きっとそうだよ!
だからなんとか三年間頑張って乗り切ろうよ!」
「昼間、駐車場で話した事もう一度説明して貰えませんか?」
「いいよ。
とりあえず公園かなにか座れるような所、
近くに無い?」
私なんかが・・」
「自分からなりたいって決心して、
今日、あの事務所訪ねたんでしょ?」
「うん、でも軽い気持ちだったし、
私より可愛い人沢山いるから、
ちょっとだけテレビに出れたら、
それでいいかなって気持ちだもん」
1週間前、
あの女社長にスカウトされた大島優里は
今日の朝方まで苦悩していた。
事務所に顔だすか、出さないかと。
芸能界に興味があったのは事実らしい。
「う~ん、今は確かに実力派女優にはほど遠いかな。
ぼくは君の将来を知っているから、
こんなにドキドキするけど、
知らない人が見たら
多分普通の女の子かな?ん?
上の中くらいかな?」
「やっぱり自信なくした」
ふて腐れたように口を尖らせる優里。
「ごめんごめん、
気のもちようで変わっていたんじゃないのかな。
チャンスがあって、
周りの人たちが大島さんを好きになって。
それで期待に答えようと努力して、
がんばろーって思って
眠っていたモノが引き立ってきてさ、
それで人気がでてきたんじゃないかな?」
ユリツキはこの時、
始めて自分の話し方、
考え方に微かな、
はっきりしない重石のような違和感を感じた。
”不器用”と、いった、
清潔な言葉では片付けられない
どこか不潔な物だった。
「そうなのかな~」優里は、
しんみりとした声で頭を傾け言った。
「フォローになってません?」
「う~ん。どうかな」
「でも、きっとそうだよ!
だからなんとか三年間頑張って乗り切ろうよ!」
「昼間、駐車場で話した事もう一度説明して貰えませんか?」
「いいよ。
とりあえず公園かなにか座れるような所、
近くに無い?」