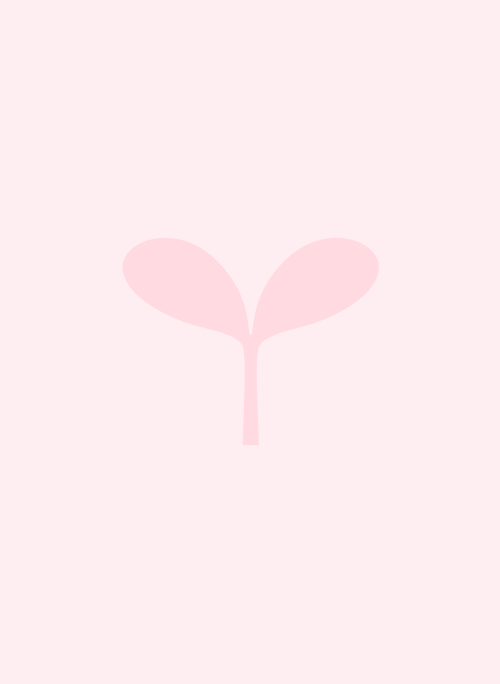置く前に前日のキャンドルが、
無くなっているかを手のひらで
パタパタ床を叩き確かめてから、
そこにキャンドルが無いことを喜び、
新しく置いていた
。
正樹は赤墨色の床に
小さな手が健気に伸びてくるのを
一日も欠かさず眺めていた。
膝を抱き爪を噛み、
”よいしょ、よいしょ”と、
ハシゴを登る罪なき、
清み切った声を聞いていた。
正樹は何をどうすれば良いのか、
分からなかった。
苦しかった。
もっと遠くへ逃げ出したとも思った。
慟哭しながら、
その小さな手にしがみ付こうかとも思った。
貧疎な作りつけの棚に、
まだ灯りが灯されていない
鮮やかな色彩の蝋燭が並んでいた。
ルビーレッド、ラズベリー、
ベビーピンク、マリーゴールド、
シーグリーン、セルリアンブルー
その場所のすべての色が、
自分をどこかに誘ってくれるて、
包みこんでくれるような
神聖な光を放っていた。
無くなっているかを手のひらで
パタパタ床を叩き確かめてから、
そこにキャンドルが無いことを喜び、
新しく置いていた
。
正樹は赤墨色の床に
小さな手が健気に伸びてくるのを
一日も欠かさず眺めていた。
膝を抱き爪を噛み、
”よいしょ、よいしょ”と、
ハシゴを登る罪なき、
清み切った声を聞いていた。
正樹は何をどうすれば良いのか、
分からなかった。
苦しかった。
もっと遠くへ逃げ出したとも思った。
慟哭しながら、
その小さな手にしがみ付こうかとも思った。
貧疎な作りつけの棚に、
まだ灯りが灯されていない
鮮やかな色彩の蝋燭が並んでいた。
ルビーレッド、ラズベリー、
ベビーピンク、マリーゴールド、
シーグリーン、セルリアンブルー
その場所のすべての色が、
自分をどこかに誘ってくれるて、
包みこんでくれるような
神聖な光を放っていた。