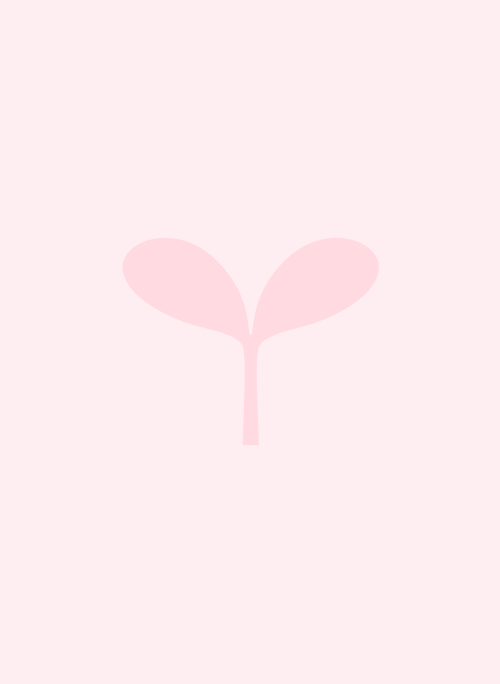正樹は
病院に連れて行かれることは無く、
赤チンキをつけられ
包帯が巻かれただけで、
その包帯は傷が癒えるまで
替えられること無く、
手垢で薄汚れていった。
「それからなんだ、
俺の当り屋人生が
メデタク幕を開けたのは」
そう言って正樹は窓際に立った。
いつもの時間帯より、
窓が濁った色だとユリツキは思い
「今日は曇りだな」
ぽつりと言った。
正樹はユリツキに背を向けたまま
灰色のトレーナーを脱ぎ
Tシャツ一枚になる。
右肘から肩にかけて
引きずられたような傷が痛々しかった。
正樹はTシャツも脱いだ。
その甘い顔に到底似合わない、
太いミミズばれのような傷が
二本背中にあった。
昇り龍の彫り物にも見えた。
わき腹から背骨辺りまで、
皮膚がめくれたまま完治したような傷もある。
小さな傷も無数にあるが、
小さな傷などまったく目立たないほどに
強烈な体だった。
二人は優里を起こさないように
気を使った足取りで表に出た。
正樹は大きく腕を広げ深呼吸をする。
清清しい空模様ではないが、
爽やかに笑顔を見せた。
「子供の頃の記憶ってさ、
面白いよな。
楽しい思い出より、
辛い思い出の方を覚えている」
ユリツキは俺達には
楽しい思い出なんてなかったんだよ、
と言いたかったが、躊躇った。
言ってしまえばまた元の、
昔の情けない自分に
戻ってしまう気がしたのだ。
母、井上公子は
正樹の傷が癒えたころから、
しきりに幼い手を取り涙を流した。
正樹の手を握り、
あてもなく徘徊した。
母が自分を見る時の目が異常に淋しそうで、
思い詰めた眼差しがあったと
正樹は記憶している。
六畳一間、
共同トイレのアパートから
表に出た時の母の軽い足取りと
長時間徘徊した後の足取りが
明らかに違うのが
子供心の正樹にもはっきりとわかった。
病院に連れて行かれることは無く、
赤チンキをつけられ
包帯が巻かれただけで、
その包帯は傷が癒えるまで
替えられること無く、
手垢で薄汚れていった。
「それからなんだ、
俺の当り屋人生が
メデタク幕を開けたのは」
そう言って正樹は窓際に立った。
いつもの時間帯より、
窓が濁った色だとユリツキは思い
「今日は曇りだな」
ぽつりと言った。
正樹はユリツキに背を向けたまま
灰色のトレーナーを脱ぎ
Tシャツ一枚になる。
右肘から肩にかけて
引きずられたような傷が痛々しかった。
正樹はTシャツも脱いだ。
その甘い顔に到底似合わない、
太いミミズばれのような傷が
二本背中にあった。
昇り龍の彫り物にも見えた。
わき腹から背骨辺りまで、
皮膚がめくれたまま完治したような傷もある。
小さな傷も無数にあるが、
小さな傷などまったく目立たないほどに
強烈な体だった。
二人は優里を起こさないように
気を使った足取りで表に出た。
正樹は大きく腕を広げ深呼吸をする。
清清しい空模様ではないが、
爽やかに笑顔を見せた。
「子供の頃の記憶ってさ、
面白いよな。
楽しい思い出より、
辛い思い出の方を覚えている」
ユリツキは俺達には
楽しい思い出なんてなかったんだよ、
と言いたかったが、躊躇った。
言ってしまえばまた元の、
昔の情けない自分に
戻ってしまう気がしたのだ。
母、井上公子は
正樹の傷が癒えたころから、
しきりに幼い手を取り涙を流した。
正樹の手を握り、
あてもなく徘徊した。
母が自分を見る時の目が異常に淋しそうで、
思い詰めた眼差しがあったと
正樹は記憶している。
六畳一間、
共同トイレのアパートから
表に出た時の母の軽い足取りと
長時間徘徊した後の足取りが
明らかに違うのが
子供心の正樹にもはっきりとわかった。