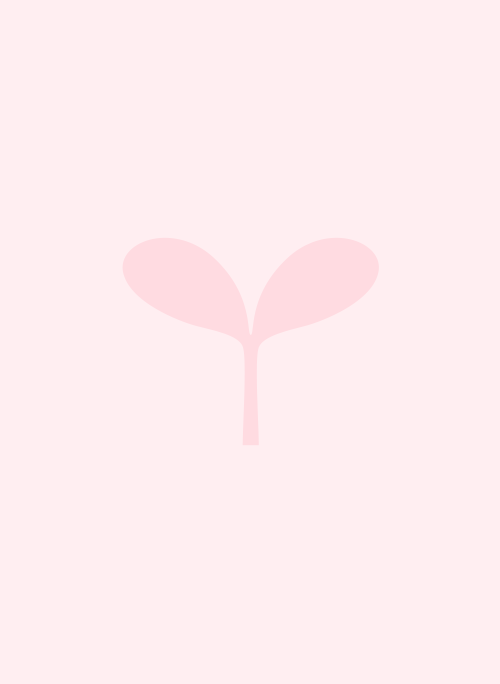車道と歩道を区切っていた縁石に
タイヤとステップが擦れ、
三人共に歩道へ投げ出され、
公子の不気味な叫び声が上がる、
健治は吸っていた煙草を路面に叩きつけ、
停車する気配がない四台目の車を
全速力で追いかけ、
トランクを怒りに任せ叩き停車させた。
母公子は呆然と直立に固まり、
正樹を顔を凝視していた。
止めど無く鮮血が滴り落ちていたのだ。
まるで赤い物が生命を得て、
重力に従い正樹の顔を
這っているようであった。
「霧が掛かったみたいに
変な感じがした。
その時、はっきり憶えているのは
足元のアスファルトが
赤く塗れていた場面なんだ」
正樹は古い傷口を、
中指で蚊にでも刺されたようにかきながら、
そう呟いた。
幼い正樹は泣かなかった、
泣くどころか、
少し笑顔に見える程
穏やかに落ち付いて立っていた。
明かに健治の方に非があるのだが、
額から血を流す幼い子供を見た
運転手はうろたえ、
謝罪の言葉で深く頭をたれた。
運転手は変人の町の住人だった。
タイヤとステップが擦れ、
三人共に歩道へ投げ出され、
公子の不気味な叫び声が上がる、
健治は吸っていた煙草を路面に叩きつけ、
停車する気配がない四台目の車を
全速力で追いかけ、
トランクを怒りに任せ叩き停車させた。
母公子は呆然と直立に固まり、
正樹を顔を凝視していた。
止めど無く鮮血が滴り落ちていたのだ。
まるで赤い物が生命を得て、
重力に従い正樹の顔を
這っているようであった。
「霧が掛かったみたいに
変な感じがした。
その時、はっきり憶えているのは
足元のアスファルトが
赤く塗れていた場面なんだ」
正樹は古い傷口を、
中指で蚊にでも刺されたようにかきながら、
そう呟いた。
幼い正樹は泣かなかった、
泣くどころか、
少し笑顔に見える程
穏やかに落ち付いて立っていた。
明かに健治の方に非があるのだが、
額から血を流す幼い子供を見た
運転手はうろたえ、
謝罪の言葉で深く頭をたれた。
運転手は変人の町の住人だった。