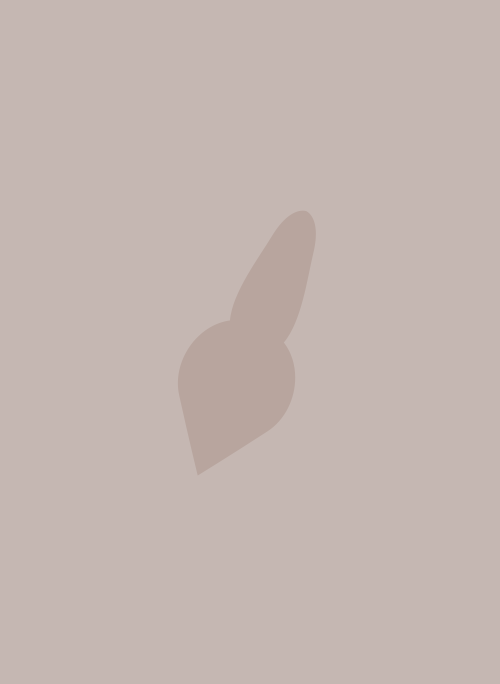黒眼鏡の外れたその顔はラーンの思っていた通り、スマルトだった。
額から流れた血で前がよく見えないらしく、近くに顔を寄せてくる。
「良くないよ! どうしてスマルトがここにいるんだよっ! スマルトは……、王様なんだよ……!」
血の飛んだ彼の手を握りしめてスマルトの躰を抱き、ラーンは下を向いた。
「どうして、僕なんか庇うんだよ‥‥」
ラーンの瞳から、涙が落ちていく。
「──大切だから」
突然、スマルトの声が上から降ってきて、ラーンは思わず顔を上げた。
「誰でも、大切なひとは守りたいと思うだろ?」
そこには、正装のスマルトが立っている。
──スマルトが、二人……?