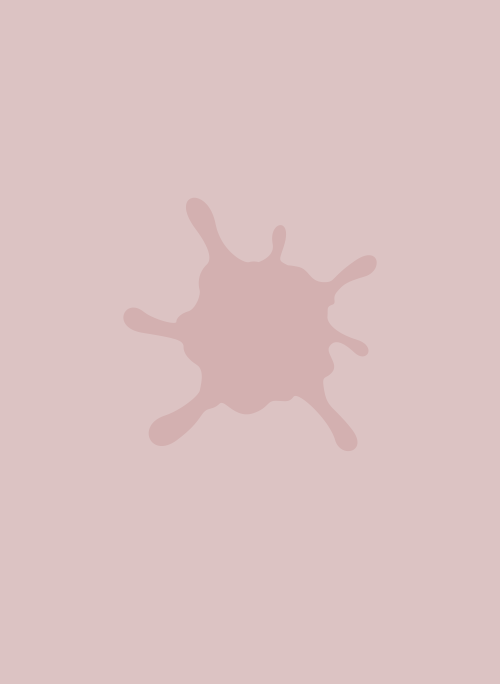紗里がこの場所へ来て数分も経たないうちにあの男はやって来た。
自分の身に起こったことが理解できず、呆然とするしかない紗里に男は話しかけた。
細くしなやかな体つきと、つり上がった切れ長の右目と眼帯の左目。笑みを浮かべる横長の口は蜥蜴を連想させた。
「あんたが新しい漂流者だね。来て早々にアレだけど、死んでもらうよ」
紗里は耳を疑った。
そんな言葉を自分が聞かされるとは夢にも思わなかった。
しかし、男の手に握られたナイフが、それが冗談ではないことを物語っていた。
振り上げられたナイフに紗里は反射的に走り出した。
追いかける男は紗里を追ってゆっくりと歩き出す。
まるで獲物をわざと逃がして楽しむように。
闇雲に走る道は続いているのか、どこへ向かっているのか分からない。
ぽつぽつと頼りなく灯る外灯は、行き先を示すことはなく、
紗里の背丈よりも高い、継ぎ目なく続く土壁や、蜘蛛の巣のように頭上に張り巡らされた電線でさえ、紗里を追い詰めていく様に視界に迫って見えた。
走り続ける疲労と恐怖で上手く呼吸が出来ず、紗里の呼吸は声音が混ざる。
酸素を無理矢理体に入れようとする度に肺が痛んだ。
不意に背後に迫っていた足音が消えた。
音だけを頼りに逃げていた紗里にとって、それは恐怖を増長させる信じがたい事態だった。
思わず振り向くと、そこに男の姿はない。
その代わりに外灯が作り出す仄かな光が、辺りを染め始めた夜の闇の中に影を描いた。
紗里の形の影と、その上に重なって通りすぎていく男の影。
影が動く意味を紗里が理解したときにはもう、男は紗里の頭上を音もなく飛ぶように越えて待ち構えていた。
自分の身に起こったことが理解できず、呆然とするしかない紗里に男は話しかけた。
細くしなやかな体つきと、つり上がった切れ長の右目と眼帯の左目。笑みを浮かべる横長の口は蜥蜴を連想させた。
「あんたが新しい漂流者だね。来て早々にアレだけど、死んでもらうよ」
紗里は耳を疑った。
そんな言葉を自分が聞かされるとは夢にも思わなかった。
しかし、男の手に握られたナイフが、それが冗談ではないことを物語っていた。
振り上げられたナイフに紗里は反射的に走り出した。
追いかける男は紗里を追ってゆっくりと歩き出す。
まるで獲物をわざと逃がして楽しむように。
闇雲に走る道は続いているのか、どこへ向かっているのか分からない。
ぽつぽつと頼りなく灯る外灯は、行き先を示すことはなく、
紗里の背丈よりも高い、継ぎ目なく続く土壁や、蜘蛛の巣のように頭上に張り巡らされた電線でさえ、紗里を追い詰めていく様に視界に迫って見えた。
走り続ける疲労と恐怖で上手く呼吸が出来ず、紗里の呼吸は声音が混ざる。
酸素を無理矢理体に入れようとする度に肺が痛んだ。
不意に背後に迫っていた足音が消えた。
音だけを頼りに逃げていた紗里にとって、それは恐怖を増長させる信じがたい事態だった。
思わず振り向くと、そこに男の姿はない。
その代わりに外灯が作り出す仄かな光が、辺りを染め始めた夜の闇の中に影を描いた。
紗里の形の影と、その上に重なって通りすぎていく男の影。
影が動く意味を紗里が理解したときにはもう、男は紗里の頭上を音もなく飛ぶように越えて待ち構えていた。