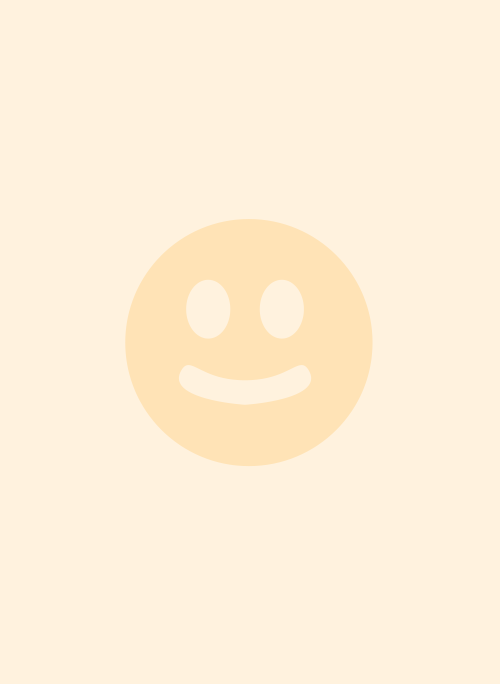浩也は歩きながら、何故彼女が特別刑務部隊の隊長なのか、疑問に思った。
難しい漢字はほとんど読めず、書類や資料整理は部下に任せっきりだし、何より巡回と称して街を歩き回り、酷い時には見知らぬ子供と一緒に公園で遊んだり、有ろう事かホームレスと昼寝をしたりするのだ。
喧嘩が強く、今までも負け無しで、テロリストの検挙率はダントツだということは知っている。
腕っぷしだけで隊長が勤まるほど甘い世の中ではないはずだ。
第一、自分はもう25になるが、彼女はまだ17歳。
車の免許すら取れない。
もしかしたらこれは嫉みかもしれない。
けれど、何かが気に食わないのは確かだった。
「浦賀浩也、ただ今帰りました〜」
いつものようにそう言いながら、街の角に聳える署に戻る。
まるで学校のような建物は、人間が増築して大学のようになっていた。
「む、ご苦労だったな浦賀三席。……ところで、麗雨はどうした?」
彼を出迎えたのは、清潔そうなストレートの焦げ茶色の髪に、眼鏡をかけた男だった。