「クビ…」
それだけは絶対に避けたい…
勇気くんだってまだ若いし未来がある。
私のせいで職を失うなんてことになったら何より私が罪悪感に飲まれてしまいそうだ。
勇気くんだって、こんなリスクが高いって知ってたのに私と付き合ったの後悔するはず。
「ねぇ、なんで私なの?」
私が問いかけると、高須くんは無表情になり、すぐに怪訝そうな顔をした。
「なんでって、清水さん。君自分がどれだけ魅力あるか分かってる?天然マイペース女子ね…笑顔も可愛いし、ふわふわしてるとこも可愛いよね?…俺の、タイプ」
「……」
簡単に可愛いって言うやつにろくなやつは居ない。
本当かもしれない。
「嬉しい?」
「誰が」
「そ?」
「……私、許さないからね。高須くんの思う通りになんか絶対にさせない!」
「清水さんだけがそう思ってたってしょうがないよ。榊原先生はどうなの?清水さんを選ぶのか、それとも自分を選ぶのか。まぁ、そんなの分かりきってるけどね?」
じゃぁまたね。そう言って高須くんは教室から出ていった。
私はなにもできずにただ立ち尽くしていた。
だって、勇気くんはさっき…
「さよならって、言った…」




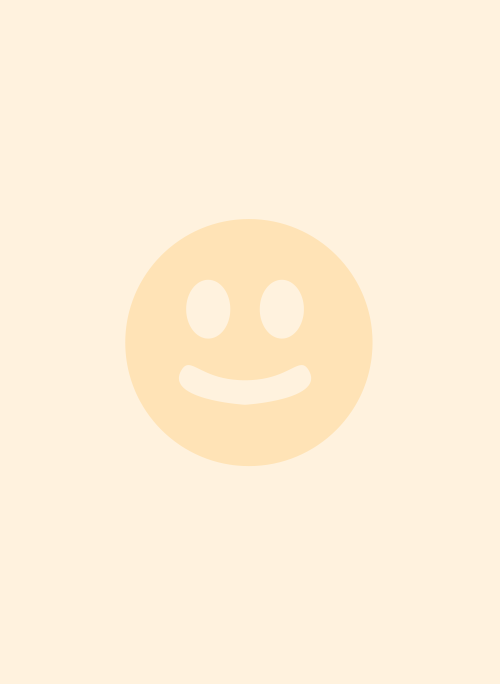
![Blue[短編]](https://www.no-ichigo.jp/assets/1.0.809/img/book/genre2.png)