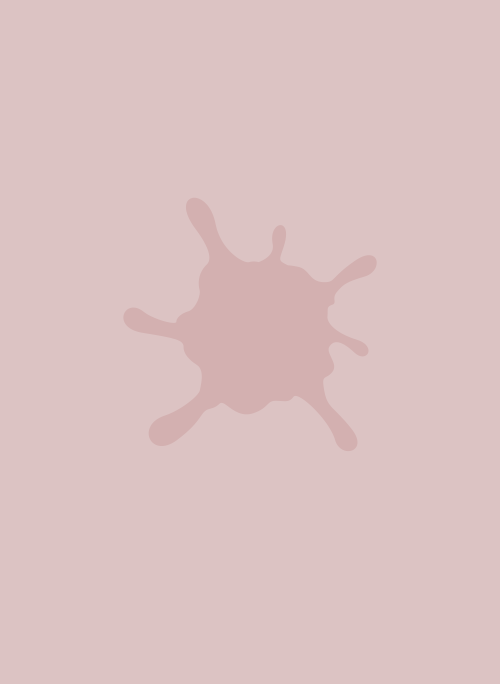「棗サン、あんたの体調気にかけてんだろ?」
拜早はこれまでの白装束紛いの服装ではなく、ゆとりのあるジーンズにロングティーシャツを着て腕組みをしつつ立っている。
「おー起きたのか、そーなんだよ、棗のやつ事務監視科の癖に差し入れ持ってきてくれるわ朝起こしに来てくれるわ…他のトコでこんなんねーってよ。俺様いい身分だね〜」
管原は少し笑って、またレポート向かった。
「あのな…棗サンがそこまですんのは…たぶん、その…あんたが好きだからだよ」
「拜早く〜んそりゃないよ」
ちょっと頑張って言った拜早の推測を管原は超軽く一蹴する。
「なっなんでそう言えるんだよ」
「………」
管原は短く黙り…
そして再びペンを握り直して薄く口を開いた。
「俺に惚れたって無駄だからだよ」
拜早は意味が分からんと顔をしかめる。
「…俺だってあんたのどこがいいのかさっぱり分かんねーよ」
「何言ってるの拜早クンこの世の中にこーんなステキガイが他にいると思っているのかい?!」
「じゃあ棗サンが惚れてもおかしくねーじゃん」
揚げ足を取られ管原は変な顔で固まる。
ふんと鼻を鳴らして拜早は座っている管原を見下ろした。
「…軽口ばっか叩いてて、どーなってもしらねーからな」
「……へっまだケツも青いボウズが知った風な口ききやがって」
逃げる様な態度で管原はガリガリとレポート用紙に突っ伏す。
そんな管原の後ろから覗き込む拜早。
「てか管原サンさっき少年の世話がどーとか言ってたけど、俺ここ来てからあんたが世話してくれた覚えねーぞ」
「寝る場所提供してやってるだろぅアハーン?!」
「そんなん世話とは言わねー!!」
二人のよく分からない言い合いが診療所の外まで響いていた。
拜早はこれまでの白装束紛いの服装ではなく、ゆとりのあるジーンズにロングティーシャツを着て腕組みをしつつ立っている。
「おー起きたのか、そーなんだよ、棗のやつ事務監視科の癖に差し入れ持ってきてくれるわ朝起こしに来てくれるわ…他のトコでこんなんねーってよ。俺様いい身分だね〜」
管原は少し笑って、またレポート向かった。
「あのな…棗サンがそこまですんのは…たぶん、その…あんたが好きだからだよ」
「拜早く〜んそりゃないよ」
ちょっと頑張って言った拜早の推測を管原は超軽く一蹴する。
「なっなんでそう言えるんだよ」
「………」
管原は短く黙り…
そして再びペンを握り直して薄く口を開いた。
「俺に惚れたって無駄だからだよ」
拜早は意味が分からんと顔をしかめる。
「…俺だってあんたのどこがいいのかさっぱり分かんねーよ」
「何言ってるの拜早クンこの世の中にこーんなステキガイが他にいると思っているのかい?!」
「じゃあ棗サンが惚れてもおかしくねーじゃん」
揚げ足を取られ管原は変な顔で固まる。
ふんと鼻を鳴らして拜早は座っている管原を見下ろした。
「…軽口ばっか叩いてて、どーなってもしらねーからな」
「……へっまだケツも青いボウズが知った風な口ききやがって」
逃げる様な態度で管原はガリガリとレポート用紙に突っ伏す。
そんな管原の後ろから覗き込む拜早。
「てか管原サンさっき少年の世話がどーとか言ってたけど、俺ここ来てからあんたが世話してくれた覚えねーぞ」
「寝る場所提供してやってるだろぅアハーン?!」
「そんなん世話とは言わねー!!」
二人のよく分からない言い合いが診療所の外まで響いていた。