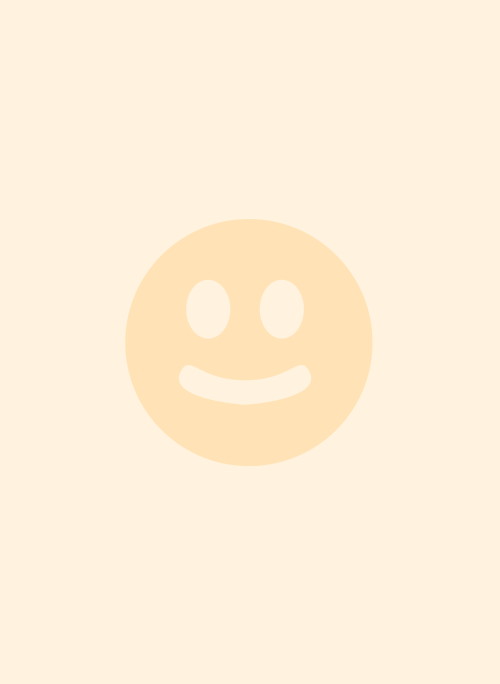『山下。今日集会から帰るとき抜け出してたよな?
どこ行ってたん?』
カーンと響く低くも高くもない声が隣からした。
この声の主は涼である。
てかこいつちゃっかり知ってるんだ。説明するのめんどくさいな。
『えっとねー…これには事情があるの。まあ話せば長くなるんだよ。』
『なんじゃあ、そりゃ。』
涼が笑った。
ドキっとした。顔がほてる。体中が熱くなって、動けなくなる。
そう、あたしは涼に恋してるんだ。
それは中学校に入学してしばらくたった日、涼があたしの落としたプリントを拾ってくれた時だった。
『これ、落ちてたよ。』
そのときに涼が魅せた笑顔で一撃だった。
あたしの中で、赤い実がパンっと弾けたんだ。
どこか幼稚で、でもどこか大人びているその一面は誰もを魅了する。
どこ行ってたん?』
カーンと響く低くも高くもない声が隣からした。
この声の主は涼である。
てかこいつちゃっかり知ってるんだ。説明するのめんどくさいな。
『えっとねー…これには事情があるの。まあ話せば長くなるんだよ。』
『なんじゃあ、そりゃ。』
涼が笑った。
ドキっとした。顔がほてる。体中が熱くなって、動けなくなる。
そう、あたしは涼に恋してるんだ。
それは中学校に入学してしばらくたった日、涼があたしの落としたプリントを拾ってくれた時だった。
『これ、落ちてたよ。』
そのときに涼が魅せた笑顔で一撃だった。
あたしの中で、赤い実がパンっと弾けたんだ。
どこか幼稚で、でもどこか大人びているその一面は誰もを魅了する。