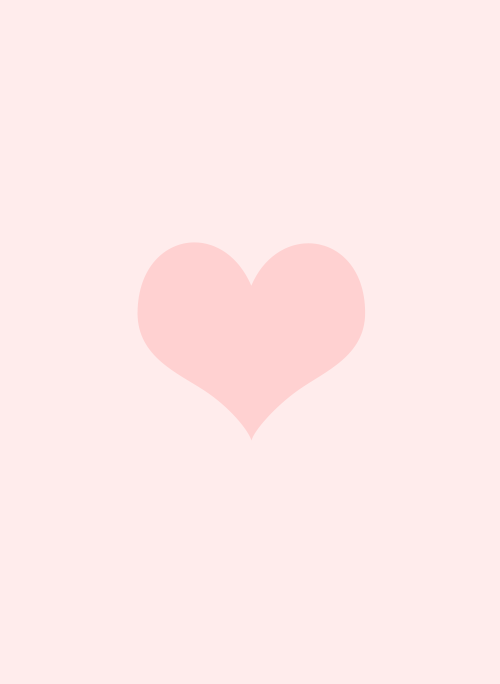「手紙、ですか?」
一柳さんは少し不思議そうな顔をして、私が差し出した封筒を受け取った。
「読んでくれるか分からないけど、でも少しは伝わるかなって思って。私はマー君の傍にいるよって」
「そうですか。渡しておきます」
一柳さんは笑顔で受け取ってくれた。
「手紙ってなんか古臭いですよね」
「そんなことありません。心がこもっていていいと思いますよ」
病院は基本ケータイ禁止だから、メールは出来ない。
というか、私は愛人のケータイの番号を知らない。
もちろん、メールアドレスも。
最初に会ったときは愛人と上手くいってなかったし、それからもなぜかお互いの口からケータイという言葉は出なかった。
でももし知っていたとしても、私はメールじゃなくて手紙を書いていたと思う。
だってメールはいつか消えるでしょ?
手紙は、無くさない限りいつまでも手元に残る。
愛人に今必要なのは機械的な文字じゃなくて、人の温かみがあるものだと思うから。
一柳さんは少し不思議そうな顔をして、私が差し出した封筒を受け取った。
「読んでくれるか分からないけど、でも少しは伝わるかなって思って。私はマー君の傍にいるよって」
「そうですか。渡しておきます」
一柳さんは笑顔で受け取ってくれた。
「手紙ってなんか古臭いですよね」
「そんなことありません。心がこもっていていいと思いますよ」
病院は基本ケータイ禁止だから、メールは出来ない。
というか、私は愛人のケータイの番号を知らない。
もちろん、メールアドレスも。
最初に会ったときは愛人と上手くいってなかったし、それからもなぜかお互いの口からケータイという言葉は出なかった。
でももし知っていたとしても、私はメールじゃなくて手紙を書いていたと思う。
だってメールはいつか消えるでしょ?
手紙は、無くさない限りいつまでも手元に残る。
愛人に今必要なのは機械的な文字じゃなくて、人の温かみがあるものだと思うから。