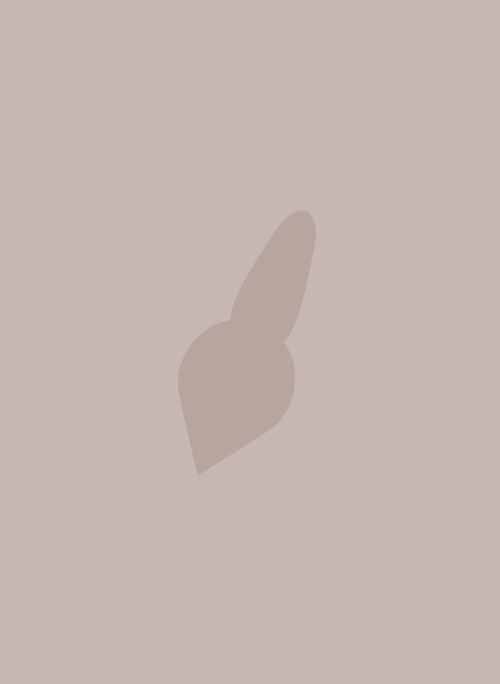『って、聞けよ。』
『あっ、ごめん…。』
『でさ、トモもアゲやっててさ、そのー…、なんていうか…。』
『今どこ?』
『えっ、ドリホ。』
『分かった、行くから、待ってて?』
『うん…。』
琴乃さんは、一方的に電話を切った。
『琴乃さん、来るだって。』
「うん…。」
それから、何分経ったか分からないけど、二人の間に会話が無かったのは、覚えている。
カツカツカツ
鋭いヒールの音に、あたしとタツは振り返った。
そこには、綺麗な白のワンピースに、ピンクのカーディガンを羽織った、綺麗でかつ可愛い女の人が、焦って走って来た。
『琴乃さんっ』
『もう、仕事帰りだったのにぃ。』
優しそうにへらへらと笑う彼女は、ヤンキーの彼女とは思えないほど、清楚で可愛らしい人だった。
『その子は?』
『アゲから助けた子。』
『おっ、やるじゃんタツぅ〜!』
『いや、しようがなかったんだよ。』
『そっか。それで?』
『それでさ…。』
タツは全部を話し終えると、俯いた。
『そーっかぁ。大変だったねぇ。それであたしに助けろって?』
『…だめっすかねぇ。』
『もちろん、いいに決まってるじゃない。ちょっとトモ。部屋まで案内してよ。』
『あっ、はい。』
あたしに待ってるように指示をすると、琴乃さんは、タツと足早に部屋への廊下を歩いて行った。
ピロピロン
メールを知らせる着信音とともに、ケータイがあたしのポケットで震えた。