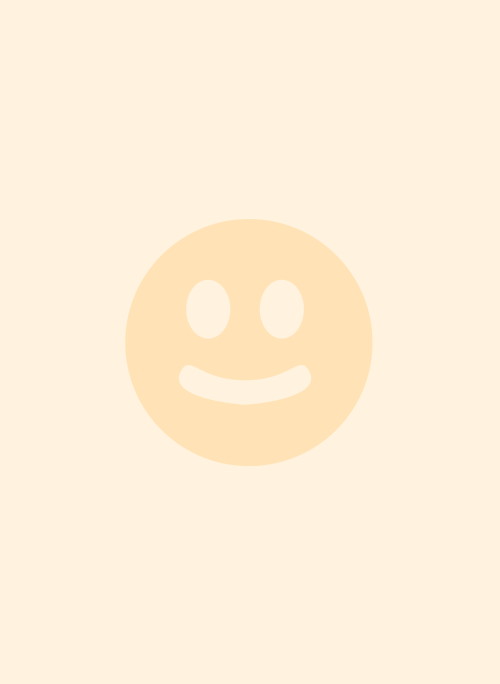ふたりが動き出したことで、他の部員も散り、真面目に練習をはじめた。
おれは壊れかけたベンチに座り、北村麗華も隣に座らせた。
「拓海さん、ありがとうございます」
北村麗華は小さい声で微笑んだが、その体は震えていた。
きっと彼女は、ずっと怯えていたんだ。
わけのわからない奴らにしつこく話しかけられ、いままで守ってくれていた拓馬もいない。
不安を押し殺して、必死に耐えていたんだ。
おれはしばらく、横に座って彼女を見つめていた。
おれにできることは、北村麗華を守り、少しでも安心してもらうことだけだった。
おれは壊れかけたベンチに座り、北村麗華も隣に座らせた。
「拓海さん、ありがとうございます」
北村麗華は小さい声で微笑んだが、その体は震えていた。
きっと彼女は、ずっと怯えていたんだ。
わけのわからない奴らにしつこく話しかけられ、いままで守ってくれていた拓馬もいない。
不安を押し殺して、必死に耐えていたんだ。
おれはしばらく、横に座って彼女を見つめていた。
おれにできることは、北村麗華を守り、少しでも安心してもらうことだけだった。