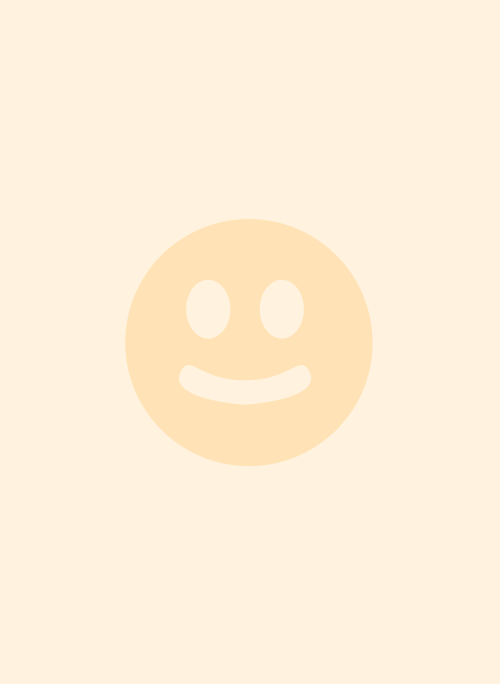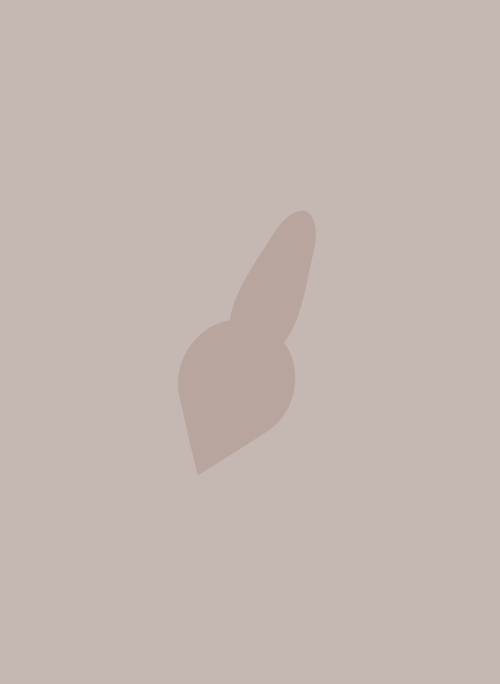――――――夢を夢と認識することが、こんなに残酷だったなんて。
ならばせめて覚めないで、残酷でいいから、俺にあの幸せな夢を見せ続けてください。
1面に咲く、スイトピーの花。
その真ん中に、彼女が立っていた。
幸せそうな笑顔が、悲しくて愛しい。
残酷なことに、彼女が笑うという光景そのものが、これは夢であると俺に認識させた。
「シュン」
柔らかいソプラノ、聞き慣れた声に安堵と愛しさが込みあげ、俺は夢の中で彼女に手を伸ばした。
「大好き」
久々に聞いた一言に、何とも言えない切なさが押し寄せる。
彼女を抱き寄せたい、そしてもう離したくない、そんな気持ちに押され、俺は彼女に手を伸ばす。
「愛してる」
俺も、俺もだよ。でも、もうお前にそれを伝えられないんだ。
ああ、どうか夢なら覚めないで。
もう届かないとわかっていた。いくら手を伸ばしても、そこに彼女はいない。触れることも、抱き締めることもできないのだ。
微笑む彼女は、ゆっくりとその姿を薄れさせていく。
その光景が悲しく、切なく、とても怖い。
待って、行かないでくれ、まだ、お願いだからまだ笑っていてくれ。
叩きつけるように叫んで、消えていく彼女を抱き締めようと腕を伸ばす。
が、抱き締めた腕の中にはただの空間しかなくて、俺は絶望したかのように崩れた。
何もないはずのそこに感じた冷たさは、あの日の彼女の体温と同じ冷たさだった。