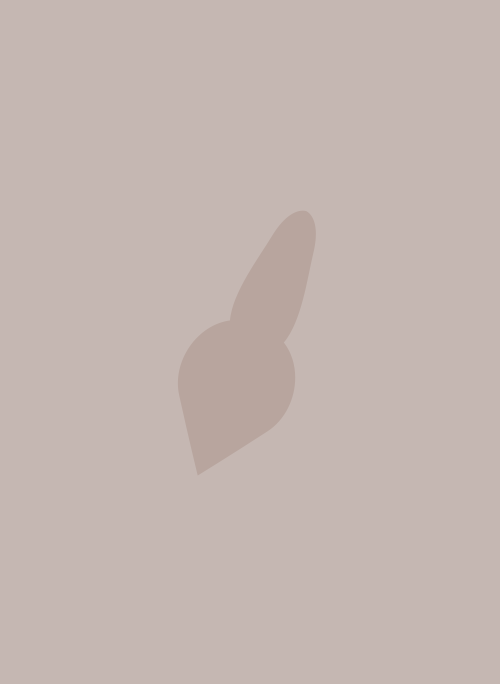ぶふっ、と沈黙の幕を引き裂いたのは明衣さんだった。
「ぶあっは、ははははっ!」
よく考えたら確かに恥ずかしい。腕一杯の缶ビールが一本フローリングの床に転がり落ちた。
「んだよお前、それ一本って量じゃねーよぉ」
明衣さんは落ちたアルミ缶を拾い上げて呆然とする俺の横をすり抜けざま、またばふばふと頭を叩くように撫でた。
「んじゃあ付き合ってもらおーかな、もう一本。…あーおもしれえ、泣けてきたぜ」
我に返った俺が明衣さんの後を追ってリビングに入ると同時に、ぷしゅんと缶ビールの気が抜ける音が聞こえた。
明衣さんが今度はヘルメットを迷い無く脱ぎ捨てる。
「誘うにも、もーちょっとあるだろうが?」
髪の毛と同じ、ふんわりした明衣さんの“耳”がぴくんと動く。
既に何本か缶を開けた明衣さんの頬はほんのり紅く染まっていた。
まだ何も飲んでいない俺まで、何故か紅くなる。
「(飲も…)」
俺が手にした缶は開けても軽快な音は鳴らなかった。