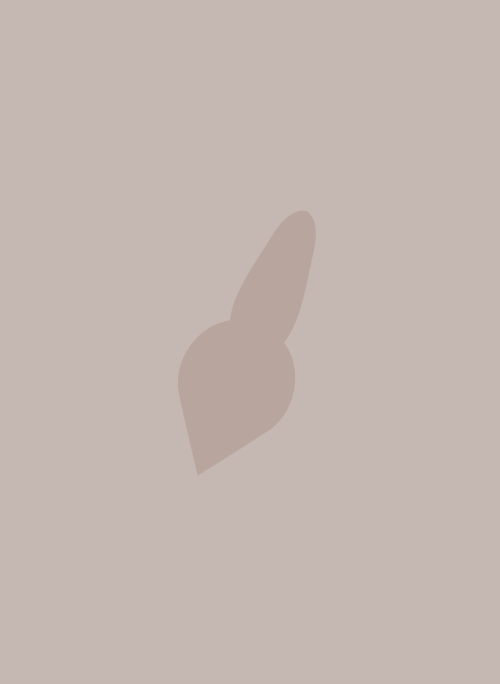「……ゆきっ!!」
あぐらをかいたまま、方向をかえた朔良がドッと傾れ込むようにして、俺の腰元に抱きついた。
「朔良…?」
普段から人懐っこくて外界へのスキンシップが多い朔良は、幼なじみの俺やメンバーに抱きついたり甘えたりすることもよくある。
だが、これは違った。
必死でしがみつく朔良はまるで大海原に放り出されたかのように、俺の身体を痛いほどに掴んで放さない。
「ゆき、俺…やだよぉっ…」
うわごとのようにつぶやき続ける朔良は小さな子供のようで。
「どーしたの、さく…言ってみ」
俺はそっと、栗色の髪が美しい頭を撫でて、「ソレ」に気付いた。