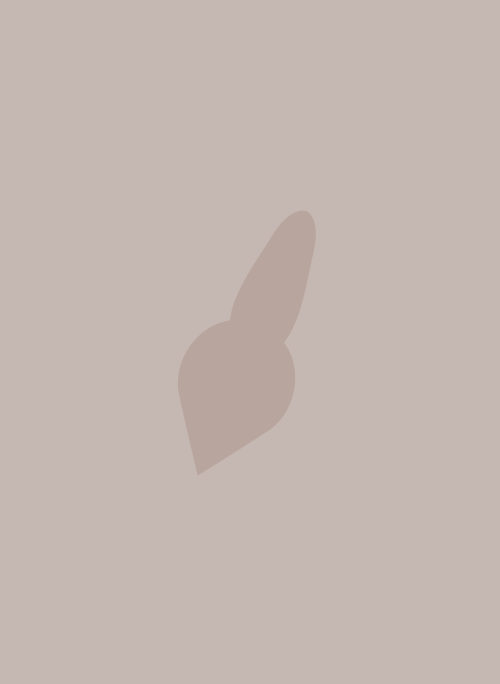ドアホールから見えたのは、彼女の姿と、彼女の手に握られた―――鋭く光るカッターナイフだった。
―――コンコンッ、コンコンッ、コンコンッ、コンコンッ、コンコンッ
「開けて、開けて、開けて、開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて」
俺の悲鳴が聞こえたのか、彼女のノックと声はもっと激しく響いてくる。
何だ、何だ、なんなんだ。俺は何もしていない。どうしてカッターなんか持っているんだ。殺す為に?誰を?俺を?いや、そんな。だって、ない。おかしい、なんで。
頭の中が完全なるパニック状態に陥る。状況がよく理解できない中で、不意にポケットの携帯が鳴った。
取り出して見てみると、サブ待ち受けに―――彼女の名前が表示されていた。
「ひっ……!!」
情けない悲鳴を出して携帯を取り落とす、その間も、ずっと彼女の声とノックの音が俺に襲いかかっていた。
―――コンコンッ、コンコンッ、コンコンコンコンコンコンコンコンコンゴンゴンゴンゴンゴンガンガンガンガンガンッ!!
「開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて」
携帯のバイブも鳴り止まないまま、恐怖を通り越して呆然とする頭で、俺は淡々とそして単純な事を考える。
―――どうして、こうなった?
―――コンコンッ、コンコンッ、コンコンッ、コンコンッ、コンコンッ
「開けて、開けて、開けて、開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて」
俺の悲鳴が聞こえたのか、彼女のノックと声はもっと激しく響いてくる。
何だ、何だ、なんなんだ。俺は何もしていない。どうしてカッターなんか持っているんだ。殺す為に?誰を?俺を?いや、そんな。だって、ない。おかしい、なんで。
頭の中が完全なるパニック状態に陥る。状況がよく理解できない中で、不意にポケットの携帯が鳴った。
取り出して見てみると、サブ待ち受けに―――彼女の名前が表示されていた。
「ひっ……!!」
情けない悲鳴を出して携帯を取り落とす、その間も、ずっと彼女の声とノックの音が俺に襲いかかっていた。
―――コンコンッ、コンコンッ、コンコンコンコンコンコンコンコンコンゴンゴンゴンゴンゴンガンガンガンガンガンッ!!
「開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて」
携帯のバイブも鳴り止まないまま、恐怖を通り越して呆然とする頭で、俺は淡々とそして単純な事を考える。
―――どうして、こうなった?