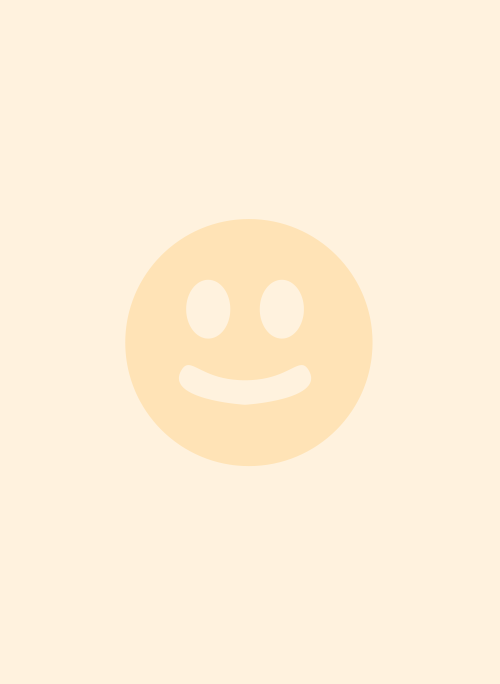“恭介さんと別れてください”
それが、手紙の書き出しだった。あの日から半年後の事だ。
“私は恭介さんを愛しています、あなたよりも”
それと、恭介と楽しそうに笑う写真が添えてあった。
「別れてくれ」
私があの手紙を持って詰め寄ると、恭介はそういった。
「なんで……」
私はしばし呆然としてしまった、知らない間に涙が頬をつたって流れ落ちる。
「私が何をしたのよ、こんなにも尽くしてきたじゃない、どこが不満だったのよ」
ねえ。
そう言って、恭介の分厚い胸板を叩いた。
それでも恭介は何も言わない。
「いやよ、私は別れない、何か言いなさいよ」
私は、しつこく何度も繰り返しそう言った。
「お前、本当に俺に尽くしたなんて思っているのか」
何度目の問いかけだろう恭介はようやく返事をした。
「はぁー?」
私はいぶかしげに恭介をにらんだ。
それを見て、ついに恭介は私に向かって怒鳴り声をあげた。
「お前を愛して尽くし続けたのは俺だ、お前じゃない、俺だ」
なに言っているの。
「お前は俺のことを愛した事など一度もない、ただ、愛して愛してとせがみ続けただけだ」
なんだ、こいつは何を言っている、これがあの恭介なの?
ごめんなさいとか、もうしませんとか、こんな女、遊びだ、本当はお前だけを愛しているとか。
私はそういう答えを期待していたのに。
何よそれ?
なんで私が責められないといけないの、浮気したのは、あんたじゃない。
「とにかく俺はもう、これ以上お前とはやっていけない」
そう言って恭介は、部屋を出て行った。
「きょうすけ……」
そう言って私は、恭介のスーツを抱きしめてへたり込んでしまった。
それが、手紙の書き出しだった。あの日から半年後の事だ。
“私は恭介さんを愛しています、あなたよりも”
それと、恭介と楽しそうに笑う写真が添えてあった。
「別れてくれ」
私があの手紙を持って詰め寄ると、恭介はそういった。
「なんで……」
私はしばし呆然としてしまった、知らない間に涙が頬をつたって流れ落ちる。
「私が何をしたのよ、こんなにも尽くしてきたじゃない、どこが不満だったのよ」
ねえ。
そう言って、恭介の分厚い胸板を叩いた。
それでも恭介は何も言わない。
「いやよ、私は別れない、何か言いなさいよ」
私は、しつこく何度も繰り返しそう言った。
「お前、本当に俺に尽くしたなんて思っているのか」
何度目の問いかけだろう恭介はようやく返事をした。
「はぁー?」
私はいぶかしげに恭介をにらんだ。
それを見て、ついに恭介は私に向かって怒鳴り声をあげた。
「お前を愛して尽くし続けたのは俺だ、お前じゃない、俺だ」
なに言っているの。
「お前は俺のことを愛した事など一度もない、ただ、愛して愛してとせがみ続けただけだ」
なんだ、こいつは何を言っている、これがあの恭介なの?
ごめんなさいとか、もうしませんとか、こんな女、遊びだ、本当はお前だけを愛しているとか。
私はそういう答えを期待していたのに。
何よそれ?
なんで私が責められないといけないの、浮気したのは、あんたじゃない。
「とにかく俺はもう、これ以上お前とはやっていけない」
そう言って恭介は、部屋を出て行った。
「きょうすけ……」
そう言って私は、恭介のスーツを抱きしめてへたり込んでしまった。