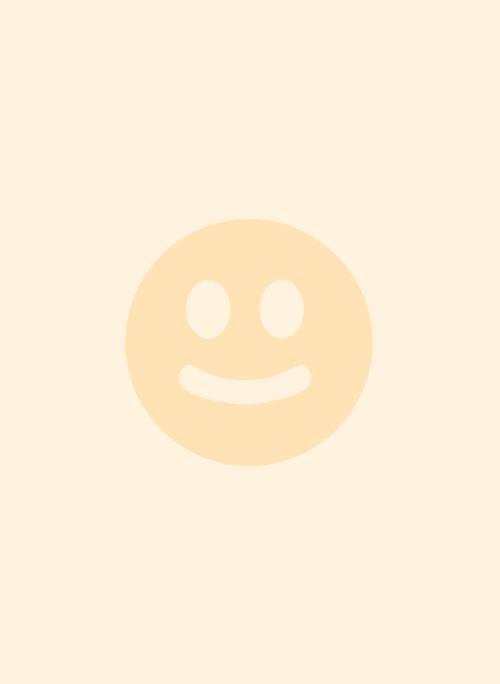「ぎゃ〜!!お、俺のケータイが…」
そう言ってラーメン鍋の底をさらってマイケータイを救助したいが…
それが望める状況下で無いのは彼の目にも明らか
昼の営業時間が終わるまで彼のケータイは煮えたぎるスープが混濁したラーメン鍋でことことと煮込まれて行き、彼もそれを見守るしかなかった。
そう言ってラーメン鍋の底をさらってマイケータイを救助したいが…
それが望める状況下で無いのは彼の目にも明らか
昼の営業時間が終わるまで彼のケータイは煮えたぎるスープが混濁したラーメン鍋でことことと煮込まれて行き、彼もそれを見守るしかなかった。