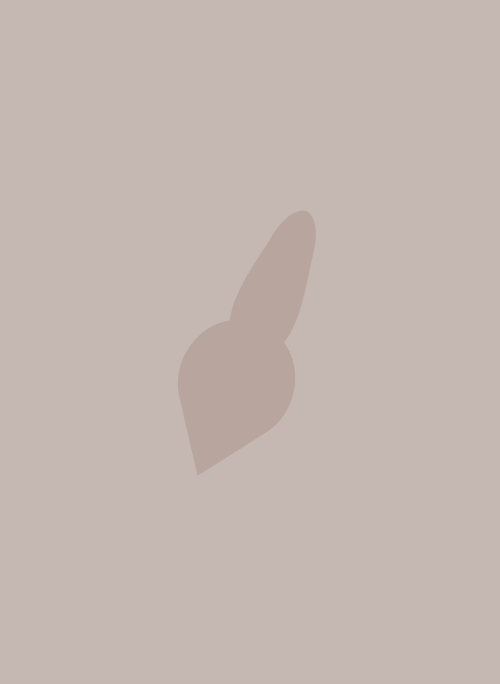朝の、すがすがしい風は、なんかの花の香気を含んでいた。遠くから、読経が聞こえた。そして抹香臭い…だとしたら、ここは寺の一室なんだろう。
で…私は誰なんだ?男は、その「こたえ」を持っていないのに思い当たった。はて、どうしたことか…夢なのか、これは?かすかな頭痛を感じた。
「目覚められましたかな?」と、老いた声が語りかけてくる。
「あっ」男は、はねるように上体を起こした。腹筋が弱っているのか、片腕を後に支えて、やっと床に落ちないでいられた。襖が半開きで、尼僧姿の人の良さそうな老女が覗いていた。その背後から光が飛び込んで眩しい。どうやら石庭の白っぽい石に日が当たっているらしい。風は、その襖が開けられたときに入り込んだのだろう。
しかし、どうしたことか…男は、紺色の浴衣を着ていたが、着た覚えも、それ以前に着ていた物を脱いだ覚えも、すっかり抜け落ちていた。
「私は、どうして、ここに?」
「門前に倒れておられた、四日ほど前の夕方」
「四日間も…それは申し訳ない」尼寺に違いない、こんな厄介は無いだろう。早々に退散しなければ…と、思ったが全身に力が入らない。
「ご無理は為さるな」と、美しい微笑を浮かべた。
若い尼僧は、茶粥を運んでくれたが、視線を上げることは一度も無かった。給仕までしてくれるような雰囲気を感じて、「一人で」と、ことわると一礼を残して退室。そして茶粥を啜り込むと、あの尼僧がまた、にこやかに現れ、膳を挟んで男と向き合った。
「あっ」と、また驚いたのは…丁髷の男が廊下を通ったからである。心で『さ、む、ら、い…』と、呟いた。俺が、もし侍なら、侍を見たからって驚くまい。と言うからは、町人か…それも違うように思う。
「そなたが病魔に添い寝されておった頃、たなごころを拝見しました。剣術に携わる御方と見受けた。おそらくは武家の出であろう。鋤や鍬などを持ったというような痕も無さそうで、それで居て、お侍を見て驚かれた」
「どうしてなのか思い出せないのです、何一つ」
「やはり」と、一つ大きく尼僧は頷いた。
で…私は誰なんだ?男は、その「こたえ」を持っていないのに思い当たった。はて、どうしたことか…夢なのか、これは?かすかな頭痛を感じた。
「目覚められましたかな?」と、老いた声が語りかけてくる。
「あっ」男は、はねるように上体を起こした。腹筋が弱っているのか、片腕を後に支えて、やっと床に落ちないでいられた。襖が半開きで、尼僧姿の人の良さそうな老女が覗いていた。その背後から光が飛び込んで眩しい。どうやら石庭の白っぽい石に日が当たっているらしい。風は、その襖が開けられたときに入り込んだのだろう。
しかし、どうしたことか…男は、紺色の浴衣を着ていたが、着た覚えも、それ以前に着ていた物を脱いだ覚えも、すっかり抜け落ちていた。
「私は、どうして、ここに?」
「門前に倒れておられた、四日ほど前の夕方」
「四日間も…それは申し訳ない」尼寺に違いない、こんな厄介は無いだろう。早々に退散しなければ…と、思ったが全身に力が入らない。
「ご無理は為さるな」と、美しい微笑を浮かべた。
若い尼僧は、茶粥を運んでくれたが、視線を上げることは一度も無かった。給仕までしてくれるような雰囲気を感じて、「一人で」と、ことわると一礼を残して退室。そして茶粥を啜り込むと、あの尼僧がまた、にこやかに現れ、膳を挟んで男と向き合った。
「あっ」と、また驚いたのは…丁髷の男が廊下を通ったからである。心で『さ、む、ら、い…』と、呟いた。俺が、もし侍なら、侍を見たからって驚くまい。と言うからは、町人か…それも違うように思う。
「そなたが病魔に添い寝されておった頃、たなごころを拝見しました。剣術に携わる御方と見受けた。おそらくは武家の出であろう。鋤や鍬などを持ったというような痕も無さそうで、それで居て、お侍を見て驚かれた」
「どうしてなのか思い出せないのです、何一つ」
「やはり」と、一つ大きく尼僧は頷いた。