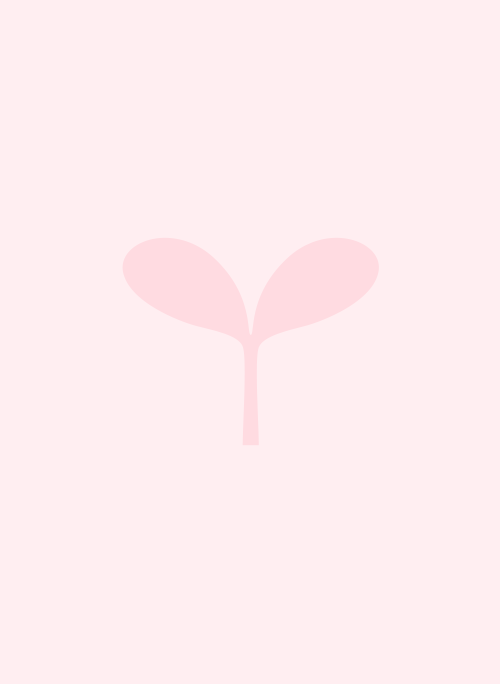「オレが、伯父さんの家を出ていっても、栖栗はもう寂しくないよなって話」
ついでに、彼が言う伯父さん、というのは栖栗の父親を指す。
彼は、高校に入ってから栖栗の家に居候していた。
栖栗は、ビー玉のように真ん丸い目を見開く。
今にも零れ落ちそうになる瞳、と、涙。
「っ‥寂しくなんか、ない。勘違いもはなはだしいわ」
栖栗は、プイッと顔を背けるとリツを抱えてさっさと歩き出す。
昔から、彼女は歩くのが早い。
だから彼は、普通に歩いていても、距離が出来てしまうことを知っていた。
マイペースに歩きながら、ずっと先にある小さな背中を見る。
「‥それに、オレも」
呟かれた言葉。
空気を吐き出しながらの、か細い声。
残り少ない日々を、彼女の隣りにいられるように、と、そう思って、彼は歩き出した。
そして──‥
茜色に消えていく。