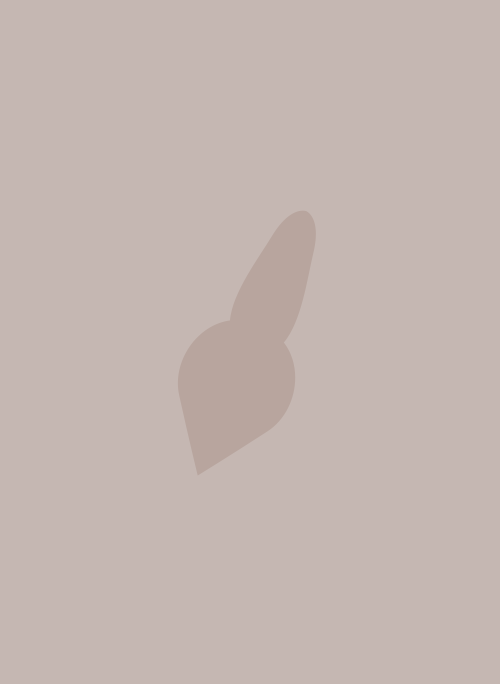『あと一週間、よろしくな。 俺の執事。』
「はい。」
再び駅に向かって歩き始めた。
さっきまでバラバラだった影は、間に2人の温もりを映してた。
「やっと結ばれてくれましたか。」
一部始終を見ていた騎馬は、仲良く歩く俺達にそう言った。
『ハハッ…騎馬には色々心配かけて悪かったな…』
「いえ、僕には心配しかする事がありませんでしたから。
凄くもどかしい日々でしたが、ようやくスッキリいたしました。」
なにげに一番喜んでるのは騎馬なんじゃないかと思った。
─それから、誰もいない最終電車に乗り、見慣れた街に戻ってきた。
行くときはあんなに長く感じた時間が、不思議なほど短く感じた。
車がまばらな駅の駐車場に着いたのは、時計の針が夜の10時を回った頃だった───。