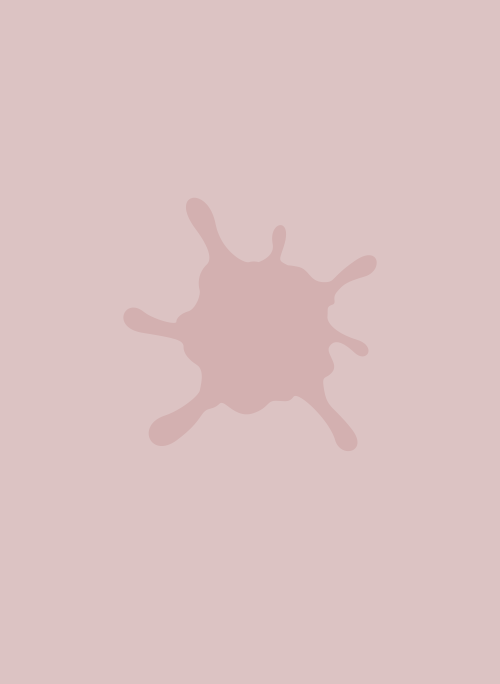その後、特に進展がないまま前半は0-0のまま終了する。
俺はベンチに戻った後、足の状態を確認しながら給水した。正直怪我と言うほどのものではない。だが打撲にも似たこの痛みは、そんな簡単に痛みと違和感は消えないものなのだ。
軽く自分で足をマッサージしていると、友里が近づいてきた。
「神崎君足大丈夫?明かに蹴られてたよね?」
友里の手にはコールドスプレーが握られており、それを俺に手渡しながらそう聞いてきた。
「大丈夫だよ。少し痛むけど大した事は無いから…」
俺はそれを受け取ると、ソックスをずらしスプレーをかける。瞬間冷却をした分、痛みが引いた感覚を感じる。そんな事をしていると、一人涼しい表情をしている直輝が俺の元に近づいてくる。
「何だかパッとしない展開だよな。危険な場面もなければ、絶好の機会もない…観客がいっぱい居るのによ」
「確かにパッとしない展開だな。でも実力が拮抗してるサッカーはこんなもんだろ?正直相手が今までの相手より一枚上手だ…思っていた以上に守りがうまいしよ。攻めは大した事ないけどな」
「まぁな。おかげで俺は暇だった…枠に入ったシュートは一本だけだったし。そう言えば、こっちの枠内シュートは何本あったか解るか友里?」
「確か5本だったかな。ロングシュートが4本と、セットプレーでのシュートが1本…でも惜しいシュートは共に0だね」
5本か…確かに惜しいシュートはこれと言ってなかった。早い段階でシュートコースを殺され、無理くり打ったシュートがほとんどで、良いシュートが打ててない。
「後半勝負と言ったところか…まぁなんとかなるだろう。俺が長澤を攻略すれば良いんだしな」
そのあと菊池先生が、ハーフタイムが終わるまでに、俺達に二つ指示を出してきた。それはコートをもっと広く使えという指示とサイドから勝負を仕掛けろという指示だ。
俺はベンチに戻った後、足の状態を確認しながら給水した。正直怪我と言うほどのものではない。だが打撲にも似たこの痛みは、そんな簡単に痛みと違和感は消えないものなのだ。
軽く自分で足をマッサージしていると、友里が近づいてきた。
「神崎君足大丈夫?明かに蹴られてたよね?」
友里の手にはコールドスプレーが握られており、それを俺に手渡しながらそう聞いてきた。
「大丈夫だよ。少し痛むけど大した事は無いから…」
俺はそれを受け取ると、ソックスをずらしスプレーをかける。瞬間冷却をした分、痛みが引いた感覚を感じる。そんな事をしていると、一人涼しい表情をしている直輝が俺の元に近づいてくる。
「何だかパッとしない展開だよな。危険な場面もなければ、絶好の機会もない…観客がいっぱい居るのによ」
「確かにパッとしない展開だな。でも実力が拮抗してるサッカーはこんなもんだろ?正直相手が今までの相手より一枚上手だ…思っていた以上に守りがうまいしよ。攻めは大した事ないけどな」
「まぁな。おかげで俺は暇だった…枠に入ったシュートは一本だけだったし。そう言えば、こっちの枠内シュートは何本あったか解るか友里?」
「確か5本だったかな。ロングシュートが4本と、セットプレーでのシュートが1本…でも惜しいシュートは共に0だね」
5本か…確かに惜しいシュートはこれと言ってなかった。早い段階でシュートコースを殺され、無理くり打ったシュートがほとんどで、良いシュートが打ててない。
「後半勝負と言ったところか…まぁなんとかなるだろう。俺が長澤を攻略すれば良いんだしな」
そのあと菊池先生が、ハーフタイムが終わるまでに、俺達に二つ指示を出してきた。それはコートをもっと広く使えという指示とサイドから勝負を仕掛けろという指示だ。