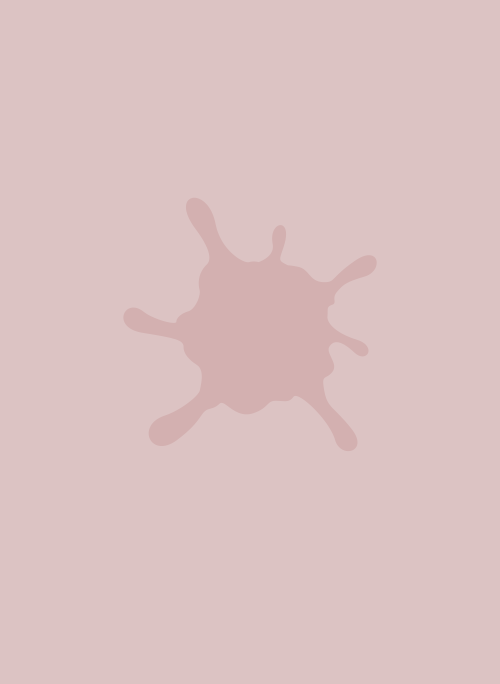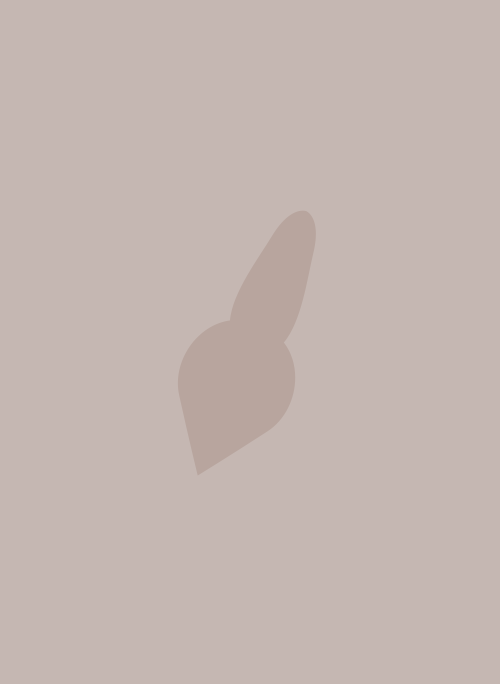季節が夏から秋に変わるころだった。
仕事を終えて、塚原は寮の自室のドアを開ける。
古い木造の寮の部屋はお世辞にも快適とは言い難かったが、これほどが丁度落ち着くのだと塚原はここを気に入っていた。
自炊のための最低限の設備は整っているし、小さな本棚と机を置くための広さはある。
畳に布団を敷き、隣に読書用の小さなランプを置けば、ゆったりとくつろいで本が読める。
帽子を取り、服を着替えて塚原は布団に潜り込んだ。
読みかけの文庫本に手を伸ばし、ペラペラとめくってみる。
風がカタカタとガラス窓を揺らす。
窓の外は良く晴れた夜空に月が浮かんでいた。
――その時。
そっと、ドアの向こうからこちらの部屋の中を伺うような視線を感じた。
空気が張り詰める。
じとりと汗をかく。
塚原が布団の中で身構え、扉を睨みつけていると、ふっとその視線は消えた。
何だったのだろうと塚原は気味悪く思いながらその日は眠りに落ちた。