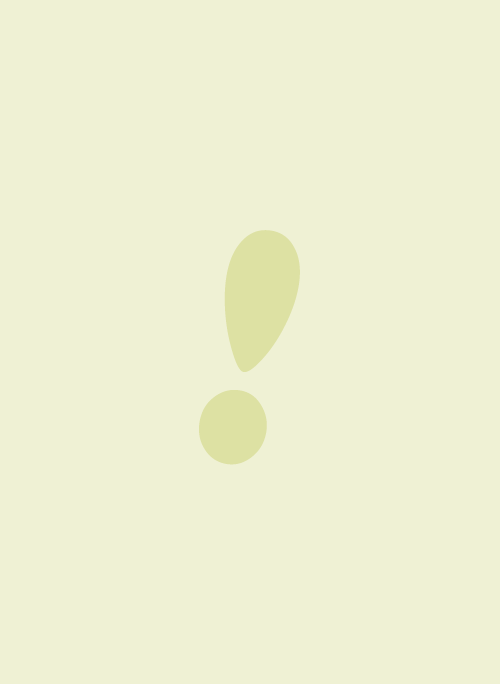『わあぁ~凄い〃
白馬は、この僕に突進するつもりらしい。
このままだと、大変なことになる…
何とかして馬を止めないと…
どうすれば、止まるのかって…
わからないよ〃
どうなっても、しかたがないのかも…』
圭介は、両手を広げて道の真ん中で、仁王たちになっていた。
『これしか出来ないよ〃
突然のことだからね』
その時の圭介は、
自分の胸に帆立て貝のペンダントが、ぶら下がっているなんてわからない。
そのことに気付いたのは、突進してきた白馬が、
圭介の目の前で急におとなしくなり、
駆けるのをやめて立止まり、いきなり圭介の胸のペンダントに、鼻をつけた瞬間だ…
白馬は、圭介のペンダントに頬をすり寄せていた。
『ええっ〃どうして…
僕の胸に、これが下がっているの。
いつから、こんなふうにぶら下がっていたのだろう。
この馬は、このペンダントの意味を知っているみたいだ。
まさかねぇ…この僕が巡礼者に見えたとはね。
それに、僕は杖も水入れの瓢箪も、持って無いよ。
まあ、どうでもいいや〃
取り敢えず、馬に乗せて貰わないとね』
圭介は、白馬をしかと見たが、その白馬の背には鞍もなければ綱も無いのだ。
そんなことでは、その白馬には乗れるわけがないのだ。
『さ~て〃
どうしたらいいんだよぉ~』