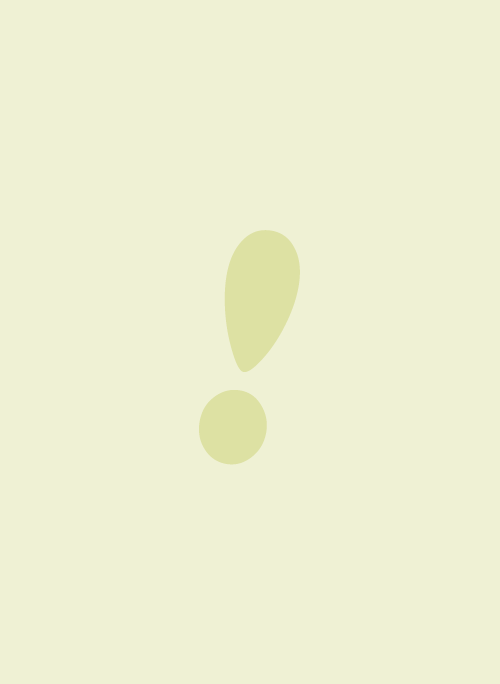すると、どうだろう。
その赤い光りは、パッシングを始めたではないか…
圭介は、驚くやら、何だか空恐ろしいような気持になり、思わず鏡を伏せていた。
『いったい、どういうことなのだろう。
僕が、合図したら…
答えてくれている。
あの星は生き物なのか…
いやいや…そんなことがあるものか。
あれは星だ、宇宙の星なのだ。
しかし、その星が僕に、
何かを知らせようと、しているのかもしれない…』
圭介が、手鏡をかざすことを止めても、
空からの赤い光りのパッシングは止むことはなかった。
どうしたものかと、考えたのだが…
圭介が考えたところで、及びもしないことだ…
それに相手は、宇宙の星なんだから、ひょっとして… 宇宙人かも…
圭介は、そんなところで納得しようと、思い始めたのだが、
だとしたら、あまりにも… ロマンがなさすぎる。