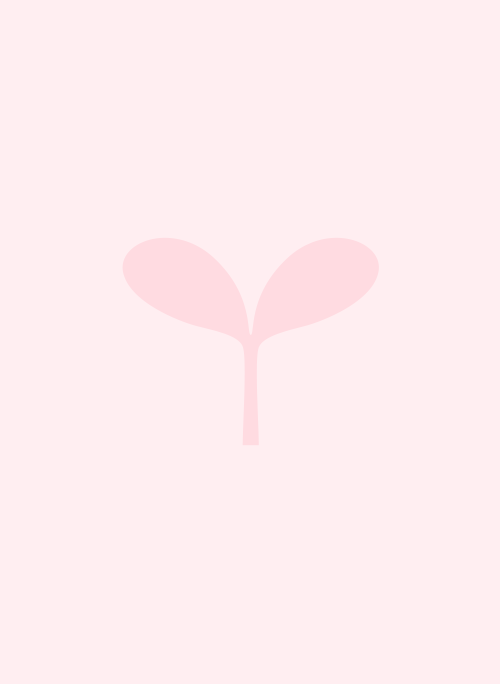彼のブロンドの髪はとても柔らかい。天使のよう、と言うには歳をとりすぎているけれど、彼の髪に触れる度にそう思った。
「恐れ多いな」
彼はそう言って笑う。
それから私の髪に触る。インクを溢したように真っ黒な髪を一房掴むと、シルクのようだと言う。
金と黒、白と黄色。私たちが持つ色は全く違うけれど、それが絡むととても美しい色を為すことを彼も私も知っていた。
「プラトニック・ラブは有り得ると思うかい?」
その問いに、私はただ微笑んだ。ベッドの上でそんなことを聞く彼が不思議だった。
「ないと思っているんだろう」
彼はいたずらっぽく笑うと(そんな年齢じゃないのにとても似合う)、私の肌に手を滑らせて遊んだ。くすぐったくて、気持ち良くて、私の体は跳ねる。
「芸術家は恋をする生き物だ。そうだろう、感情を最も揺り動かすのは、誕生と死、そして生けるものへの愛なのだ」
唇が触れるほど近く、私の耳元で彼は熱っぽく囁く。
「恐れ多いな」
彼はそう言って笑う。
それから私の髪に触る。インクを溢したように真っ黒な髪を一房掴むと、シルクのようだと言う。
金と黒、白と黄色。私たちが持つ色は全く違うけれど、それが絡むととても美しい色を為すことを彼も私も知っていた。
「プラトニック・ラブは有り得ると思うかい?」
その問いに、私はただ微笑んだ。ベッドの上でそんなことを聞く彼が不思議だった。
「ないと思っているんだろう」
彼はいたずらっぽく笑うと(そんな年齢じゃないのにとても似合う)、私の肌に手を滑らせて遊んだ。くすぐったくて、気持ち良くて、私の体は跳ねる。
「芸術家は恋をする生き物だ。そうだろう、感情を最も揺り動かすのは、誕生と死、そして生けるものへの愛なのだ」
唇が触れるほど近く、私の耳元で彼は熱っぽく囁く。