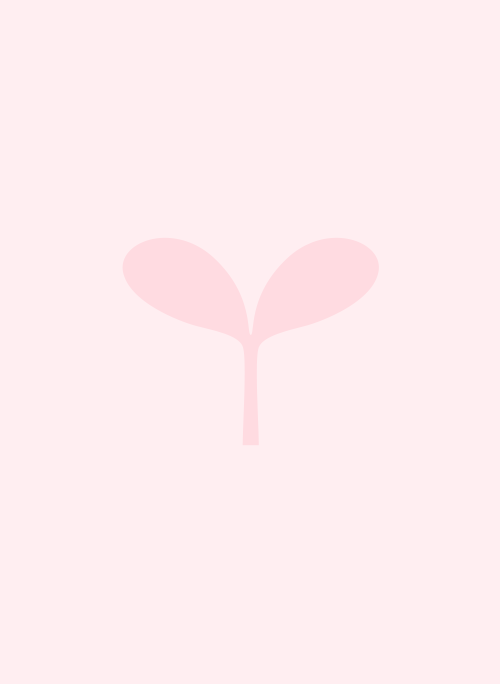案の定、白峰家のベーゼンは「違って」いた。
同じ建物の同じ部屋にあるとは言え、窓から入る日光の浴び方は違う。雨が降れば、増して日本の梅雨だ、木が吸収する水分の量は異なってしまう。それがわずかな音とタッチ、響きの違いとなる。
「わずか、だけれど」
彼女は苦笑いして、また俺の向かい側に立った。
「これでは、きりがない」
「でも、こっちは職人です。しかも恩師の後を継いだ仕事です。妥協はできない」
口にしてから、少し照れた。どうもむきになってしまう。
「矢治さんに、顔向けできませんから」
明かりの必要になる時刻まで、ずっとピアノを触っていた。ベヒシュタインに、グロトリアン。良いピアノだ。優しい顔つきをしている。
「顔」
出された軽食を口にし、そんな話をしたら、彼女は切れ長の眼を丸くした。
「ベヒシュタインは、そう、とても涼やかな顔をしている」
「音、ではなくて?」
「そうかも知れません。どこにいても周りに流されず自分を貫くような、芯の強い女性のよう」
俺がどんな顔をしていたのか、彼女の口元が緩んだ。
「フランス語では男性名詞よ、ピアノ」
俺は、狐につままれたような顔をしていたに違いない。危うく、美味いケーキを落としそうになる。
同じ建物の同じ部屋にあるとは言え、窓から入る日光の浴び方は違う。雨が降れば、増して日本の梅雨だ、木が吸収する水分の量は異なってしまう。それがわずかな音とタッチ、響きの違いとなる。
「わずか、だけれど」
彼女は苦笑いして、また俺の向かい側に立った。
「これでは、きりがない」
「でも、こっちは職人です。しかも恩師の後を継いだ仕事です。妥協はできない」
口にしてから、少し照れた。どうもむきになってしまう。
「矢治さんに、顔向けできませんから」
明かりの必要になる時刻まで、ずっとピアノを触っていた。ベヒシュタインに、グロトリアン。良いピアノだ。優しい顔つきをしている。
「顔」
出された軽食を口にし、そんな話をしたら、彼女は切れ長の眼を丸くした。
「ベヒシュタインは、そう、とても涼やかな顔をしている」
「音、ではなくて?」
「そうかも知れません。どこにいても周りに流されず自分を貫くような、芯の強い女性のよう」
俺がどんな顔をしていたのか、彼女の口元が緩んだ。
「フランス語では男性名詞よ、ピアノ」
俺は、狐につままれたような顔をしていたに違いない。危うく、美味いケーキを落としそうになる。