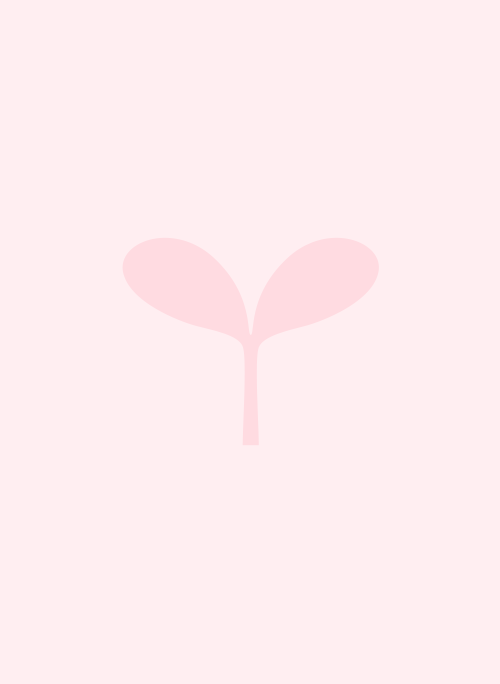「さて、合歓が来たことだしお茶を入れよう」
備え付けられている簡易キッチンのような場所に移り、お茶を入れ始めた。
「いや別にいいよ。邪魔しているし」
「そんなことない。せっかく来てくれたのだから」
慣れた手つきでお茶を入れる姿は皇子には程遠く、親近感がわく。
わたしの前に置かれたカップ。一口飲むとほろ苦い味で広がる。
わたしはこれくらいの味が好き。甘いミルクティーよりもブラック派だ。そんな好みを見通したかのような味だった。
「美味しい。皇子にしておくのが勿体ないくらい」
「そんな風に誉められたのは初めてだ」
どこからともなく笑みがこぼれる。
和気藹々とした雰囲気で話をした。
「リュイスもしっかり仕事しているんだね。やっぱスゴいよ」
「しなければならないからな。そのために生まれてきたようなものだから」
生まれた時から将来が決まっている。わたしとは違う。
いくらリュイスがお茶入れるのが上手くって、少しへたれでもそこは皇子なんだと思い知らされる。