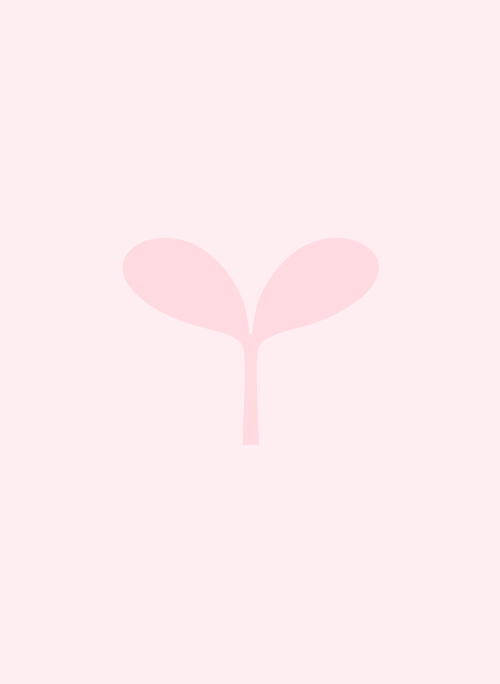「そなたたち、朝から何用だ」
皇王と皇妃さまの部屋は、さすがというか、この室だけでパーティーが開けそうなくらいだった。
案内だけのリュイスはドア近くに立ち、近くまでは来なかった。
一方のこの部屋の主二人は食後の飲み物を飲んでいたようだ。決して楽しそうな雰囲気ではないが。
「用があるのはわたしです。彼には案内をしてもらって……朝の忙しい時間にすみません。でもどうしてもお話がしたくて」
「何を」
一口、カップの飲み物を啜り、こちらに問うた。
「昨日のことです。わたしは皇妃さまがどんな人か分かりませんでした。もちろん今もよくわかりませんが。でも環境の違う場所に来て、適応を求められても無理があるのは分かります」
目線をカップやスプーンに移す。
「様々なマナーすら違いますから。わたしの場合今も苦労してます。でも自分の今までの生活に執着や未練がなかったので、受け入れることができました。皇妃さまはもしかしてまだ、受け入れることすらできていないのかもしれません」
相変わらずの危険な賭け。
わたしの首が飛ぶかもしれないとも思う。