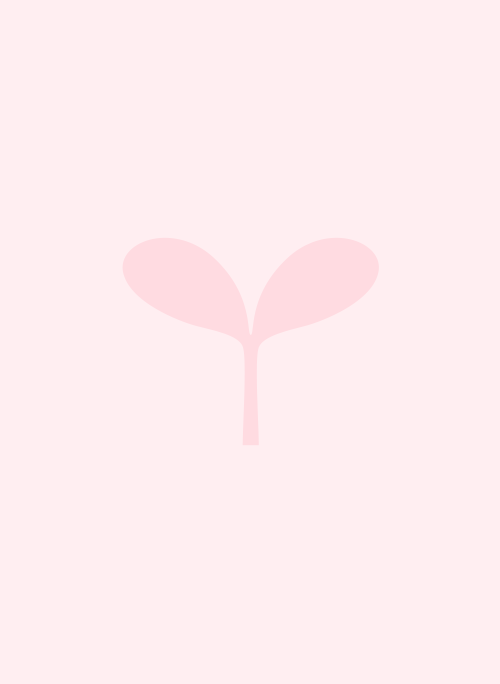「ねぇ、リュイス。もしわたしが皇妃さまならこんなこと耐えられないよ。フロウに対する憎しみもわかる気がする」
「そうだね、我が母ながら哀れに思うよ」
皇妃さまにはきちんとした言葉で伝えないといけないと思った。
それにしても、リュイスもある意味可哀想。そんな親から生まれてきて。
「昔、なんで母親に愛されなかったんだろうって思った頃があったんだ」
リュイスがわたしの手を握る。どこか震えている。
「真実を知った時、母親から愛情をもらうのは不可能だっておもった。そしたらフロウが話してくれたんだ」
「何て?」
「おれにも運命の乙女が現れる。その人がおれを愛してくれるって」
笑顔で話す姿を見て恥ずかしくなった。だってそれ、わたしでしょ?
「でも母のことがあったから心配だったんだ。そしたら、不安が消える以上にその人を愛せばいい。愛したらその分、愛されて返ってくる。愛し愛された両親から生まれた子どもはまた愛を知って生まれてくる」
悲しみの輪廻はおれが断ち切ればいい、リュイスは笑顔でそう話した。