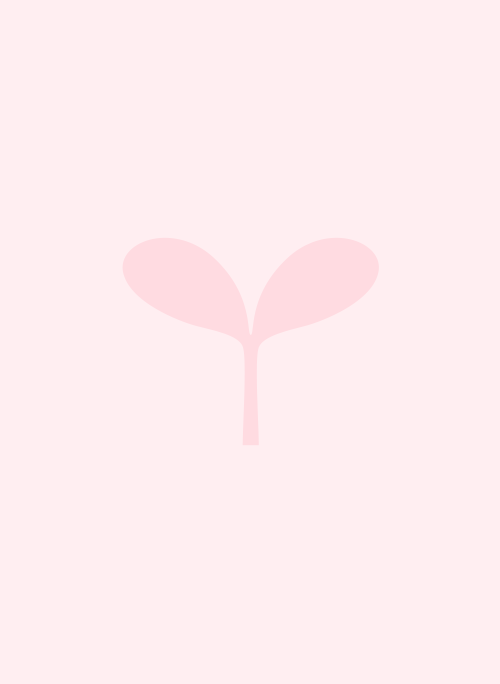今思っていたことを話すと、意外にも簡単に納得してくれた。
「どこかの貴族の人だった。銀色の花に蔦が絡み合う章を付けていた」
「それが家紋だとすると、探せばすぐ分かる!」
当事者に話が聴けない今、一番頼りになるであろうは、その貴族の男。
人に聞くとすぐに分かった。その家紋がある家はもちろんただ一つ。
エッカルト公爵家。そしておそらく、マナちゃんを助けたであろう人物はその公爵の息子であり、彼もまた侯爵の爵位を持つという。
身分的に考え、問題の神祇官の家にだって訪れる可能性はある。
たった少しの時間でそれだけのことが分かってきた。
それは暗闇に光が差し込んできたかの如く、希望に満ち溢れている。
そのことが分かるとすぐにわたしたちは街の方へ向かった。
市場の多い通りを過ぎ、貴族たちの住まう高級住宅街へと差し掛かる。これまでとは違った雰囲気にお互い、息をのみこむ。
怖気付きそうなわたしと違い、マナちゃんは見るモノが珍しいのか、逆に落ち着かない。
しかしながら、目的地に到着すると今度は別の意味で落ち着かなくなってきた。
「どうやって入るんだろう」
そう零した通り、背の高さよりはるかに高い壁に大きな門。門の隙間から見える屋敷の中は、建物がとても小さく見える。
ここにきてまさかの初歩的な問題にぶち当たるとはだれも思わなかっただろう。