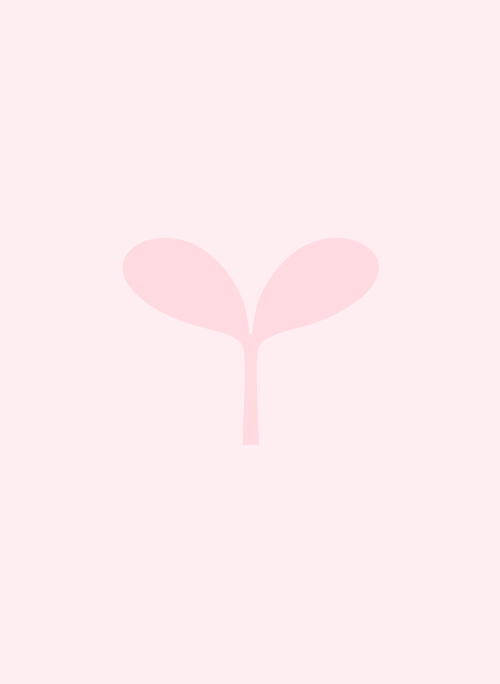「愛されることなんて、知らなかったから。誰かに必要とされればいいと思ってたんだ。だって秘玉の妃なら、俺を必要としてくれる」
その話を聴いて思い出す。
彼は愛に餓えていた。親の愛が貰えず、小さいころから“将来現れる妃”にそのよりどころを求めていたこと。
だがそれは、親に愛を求めるそれと同じ。決して恋ではないと。
「合歓は、役目じゃなくて普通に傍にいてくれた、それが嬉しかったんだ」
「その気持ちならわたしも分かる。つまらない日常にわたしという存在の必要性が見いだせなかったことがあった。だから、傍にいてくれるだけってすごく救われる」
「俺たちは似たもの同士だね」
そう言って目があった。優しく笑う彼は、今までで一番素敵に見える。
「だから恋に落ちた」
手を取り、そとの月を眺める。どうしてこうも身近な人に思えるようになったのかしら。
「愛を求め、恋をした。なら普通の夫婦みたいになってもいいんじゃないって思ったんだ」
彼の言う普通とは、国などのしがらみもなく、唯お互いを必要とする存在のことなんだろう。
「そう、それがわたしも言いたかった」
薄暗い部屋の中、月明かりが差し込んでくる。その時、わたしたちは新たな誓いを立てた。
「なら、二人だけの時は、普通の夫婦になろう」
「……その言葉、とてもうれしい」
二人だけの誓い、わたしたちは誓いの口づけを交わす。
この時だけは、ただお互いの愛に溺れてもいいと信じて。
その誓いは新たな絆になる。そう信じて、初夜は過ぎていった。