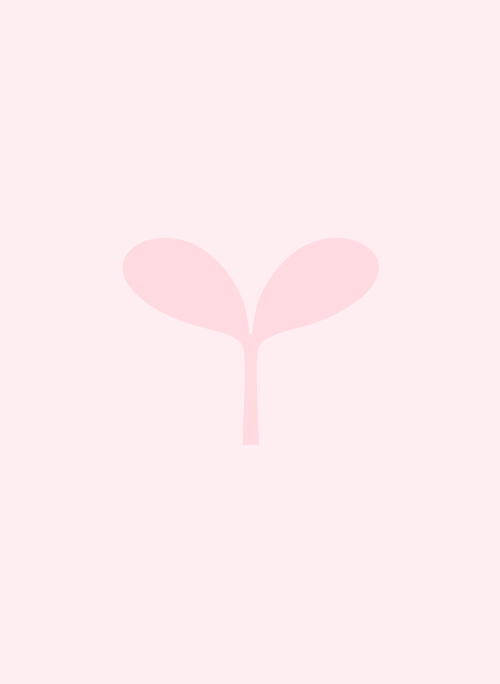昼間は感動が過ぎ去り、あっという間に夜になる。
やっぱりそこにいるのは、わたしではない別のだれかのように感じた。
わたしじゃない人が、わたしを演じているような感覚。
「なんか別世界にいるみたいだったわ」
「確かに今日みたいな日は一年にあるかないかの騒ぎだった」
夜にあったパーティーは国の重鎮たちが集まっての会食形式で、はっきりいってろくに食べれない。
それなのに、気分はもうお腹一杯になっている。普段と違う雰囲気だったせいかもしれない。
そんな他愛もない話をしながら、わたしたちは部屋に戻って行った。
式を迎えたが、部屋は変わらず、離れの宮の一室。リュイスが転がり込む形になる。
二人でその部屋まで戻って、今日一日を振り返ってみた。
「今でも損じられないことがあるの」
「ん、何?」
「だって皇族の結婚なんて、結婚というよりも儀式みたいなんだもの」
女神にこの国の繁栄を誓う、一般人として育ってきたわたしには少し、いやかなり受け入れがたい事実だった。
こんなこと言うべきではないのはわかっているのに、未練がましい。
「この国ではそれが普通だから、俺には分からないけど、合歓となら普通の夫婦になりたかった」
「普通の?」
「だって普通の夫婦は愛の誓いを立てるんだろう。最初は、傍にいてくれるだけでよかった、心のよりどころになってくれるだけで」
遠くを見ながら、リュイスは語り始めた。