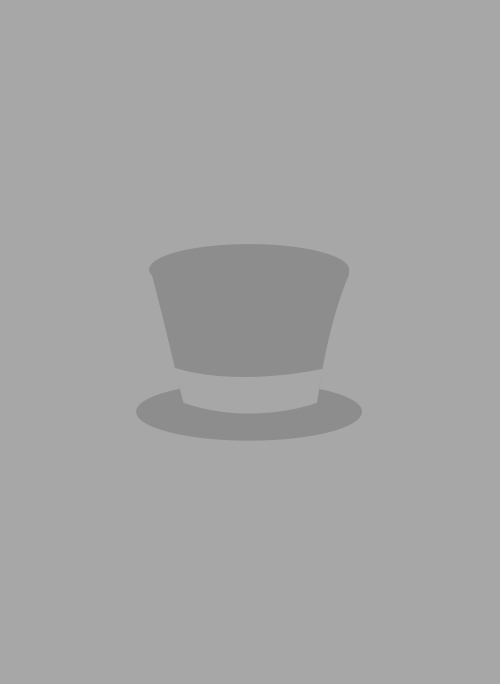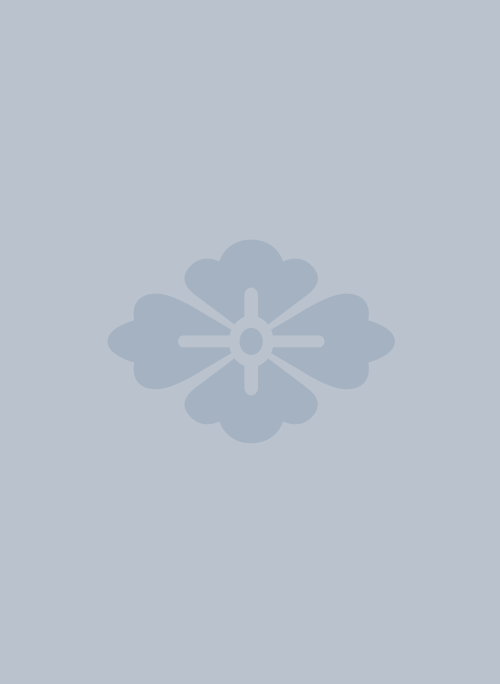屋敷の外で、普段着のままでは分からなかった、彼女の『粗』。
それが、長きに渡る歴史を受け継いだこの屋敷の中では、無惨なほど露わになっていた。
教養の無さ。
人間としてのレベルの低さ。
気品とはおよそ無縁の、持って生まれた卑しさといったものが、
彼女をこの屋敷の中で哀れなほど浮かせていた。
蓮っ葉なのも、外では彼女の魅力の一つにも感じたが、今ではただ下品にしか見えなかった。
目が覚めるような思いで、十郎はどうして彼女を家族に紹介しようなどと思ったのか、自分でも疑問に思った。
無情にも、忘れてしまったのだ。
ただ、辞めておいて、正解だったとは思った。
自分が恥をかくだけだ。
十郎はいつしか謝りながら泣いていた彼女を宥めて、
適当な理由を付けて家まで送り届けた。
彼女に着せた着物は、あげるからと言って、その後は会わなかった。
手切れ金代わりだった。
売れば、車が買えるくらいの金額にはなる。
その後しばらくは、女遊びは控えた。