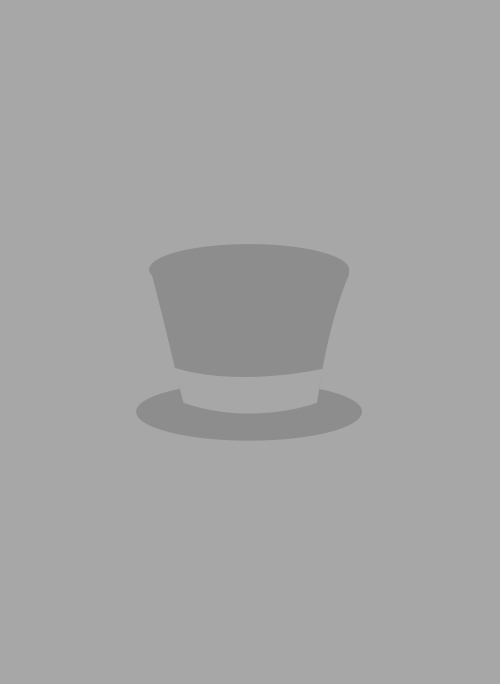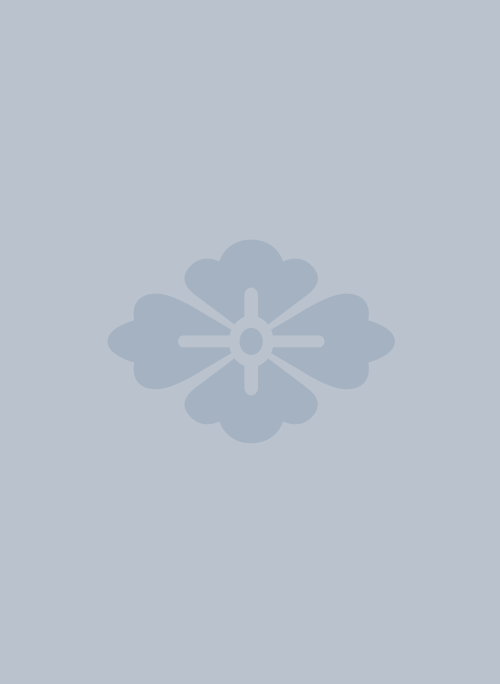すると、さっさと十郎は退室して、お直しから戻ってきた彼女に、あっさりと別れを告げた。
もうすぐ大金持ちの旧家の奥方になれるかもしれないという夢を見ていた女は、
予期せぬ突然の展開に、慌てふためいて訳も解らず弁解し始めた。
何か自分はいけない事をしたか。
何がいけなかったのか。
しかし、十郎の耳には入って来なかった。
別に、彼女がこれといって悪い事をしたわけではない。
気に障った事も、特には無いし、彼女がしなだれるように媚びてくる姿も、まんざらでもなかった。
しかし、彼女と自分は生きる世界が違うのだと、はっきり分かってしまった。
必死な様子で何かを喚いている彼女の目には、だんだん本物の涙が浮かんできたが、
十郎はそれすら軽く受け流した。
あまりにも次元の違う話だったからだ。