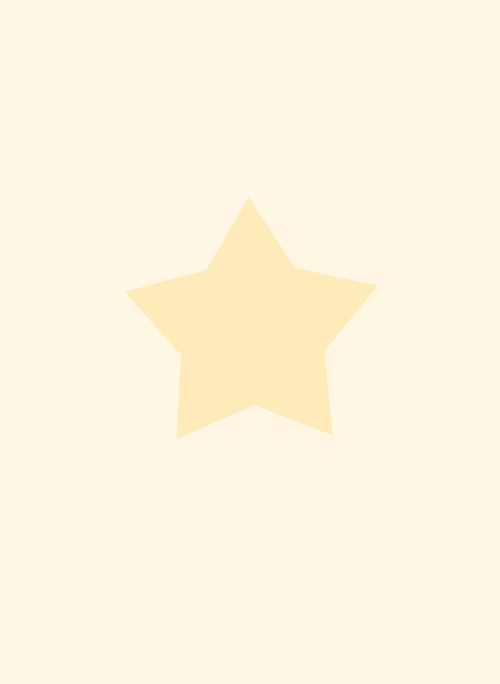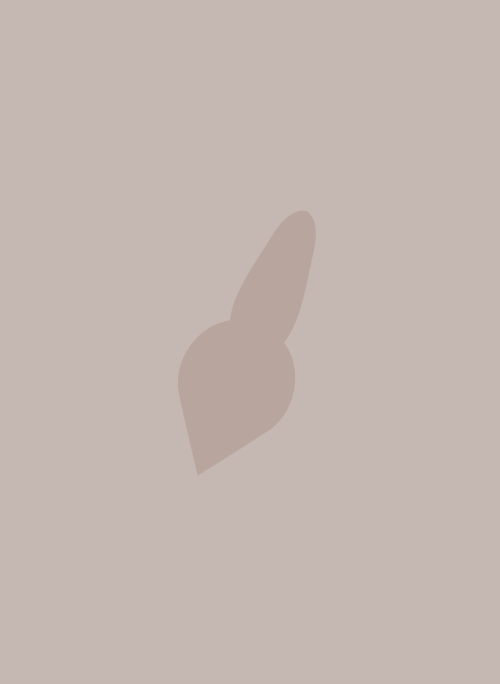なるほどそうかと小夜の言う通りに、次の朝から吉平は、少し足を伸ばして、近くの公園にまで出かけるようにした。下界に下りて、始めて見るこの公園には、相当に樹齢を重ねた樹木が植えられていて、外部の雑音から隔離された趣がある。どちらかと言えば、早朝のこの公園は、心奥に浸る詩人や作家好みの感がある。早朝の公園の人影は、吉平の教室よりも疎らであった。吉平は、ベンチに腰を下ろして、獲物と出会うタイミングを待った。その姿は、どことなく、本人とは裏腹に、初めて親の手を離れて、幼稚園に放り出された幼児の風情を漂わせている。犬の散歩をしている貴重な老夫婦に、吉平は、笑みを浮かべて会釈を送る。吉平には間を取る犬もない。タイミングを狙って、獲物を狙うかのように、民に視線を投げつけ、一人でぽつんと腰を下ろしている吉平の姿は、詩人や作家には到底できない、これまた異様な臭気を放っていた。老夫婦は、吉平をちらりと見下ろして、何やらひそひそ話をしながら素通りしていった。「民に出会うには時間がかかります」と、小夜に言われた吉平は、公園のベンチに通ったのである。今回で何度目かは記憶にないが、そろそろ面識は芽生えたものと吉平は判断した。そして吉平は、初めて老夫婦に声をかけたのである。
メニュー