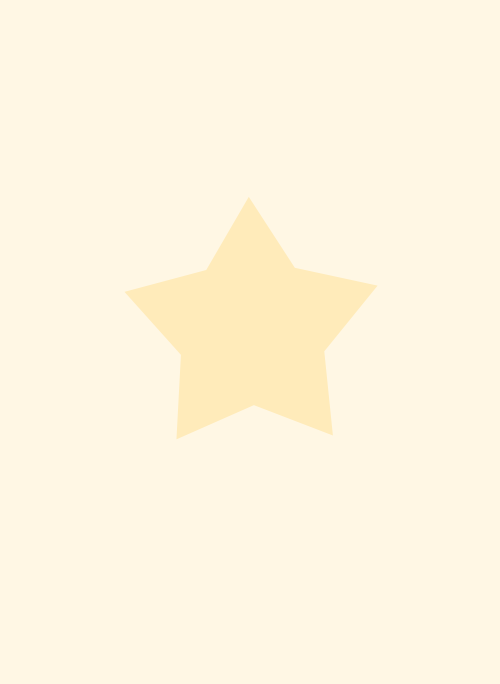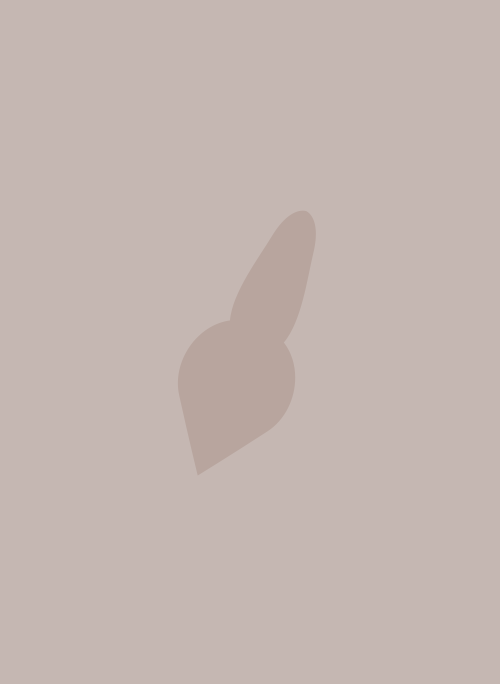その住処は、二人が座って鼻を付き合わせるほどの広さである。地面には、解体した段ボールを重ねて敷き詰めてあった。隅には、似合わず一枚の垢にまみれた毛布が畳んであった。洗面道具等の生活用品ですら見当たらない。いわば、極致に近い空間である。主も考えたのであろう、主の住処は、公園を照らす灯りのそばにあった。その照明灯の光が、ビニールを透過して内部をぼんやりと照らしている。絵の具の臭いと、腐った生ごみに顔を突っ込んだような臭いがかき混ぜられて、この空間にこもった空気は、呼吸に必要な空気さえ吸い込めないほどである。
「さあ、どうぞ」と、主は、絵の具、筆、キャンバスを足で隅に押しやり、吉平の座る地面を開けてくれた。ぼんやりとした間接照明の中で、鼻を突き合わせた吉平は、改めて主のみすぼらしい輪郭を捉えた。その刹那、吉平の威厳は、蘇ったのである。腑抜けていた吉平の背筋は、ぴんと延び、例のように、ステッキを小脇に抱え込んで、主を見下ろしたのである。吉平は、口を開いた。
「さあ、どうぞ」と、主は、絵の具、筆、キャンバスを足で隅に押しやり、吉平の座る地面を開けてくれた。ぼんやりとした間接照明の中で、鼻を突き合わせた吉平は、改めて主のみすぼらしい輪郭を捉えた。その刹那、吉平の威厳は、蘇ったのである。腑抜けていた吉平の背筋は、ぴんと延び、例のように、ステッキを小脇に抱え込んで、主を見下ろしたのである。吉平は、口を開いた。