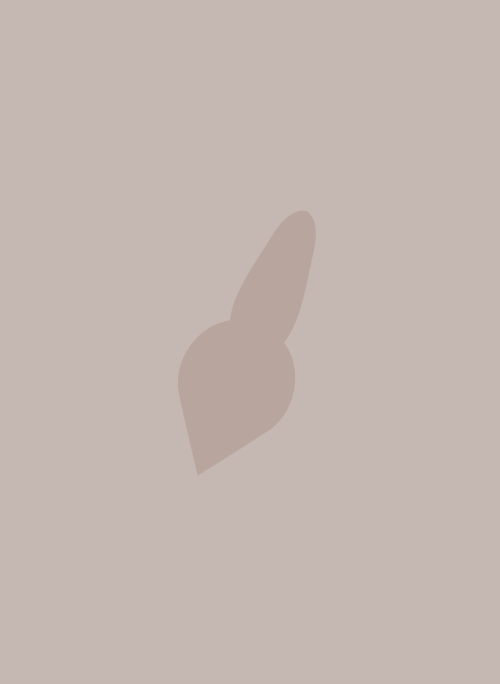「ね…安藤君。」
「ん?なに??」
彼は整った眉毛をヒョイっと上げて見せた。
「あの…ね。」
「うん?」
「訊きたいこと…あるんだけど…」
「何だい?セイセイ。」
「あの…
どうしてなの?」
もうここまで言ってしまった。
もはや後には戻れない。
「え?何が?」
「…どうして…私なんかに優しくしてくれるの?」
安藤君の顔つきがやや真剣になる。
でも、私はまだまだ訊き続ける。
「どうして…私なんかと話してくれるの?」
「…………」
「どうして?わ、わからないよ…全然わかんない。」
安藤君はただ黙りこくって、私の言葉に耳を傾ける。
私も、ただ一言訊くだけだったはずなのに、
なんだか口を開けば、感情が次から次へと溢れ出すみたいで。
「だって…私なんかと話しても何も得なんてないし、
たいして楽しくないし…
安藤君は……どういう気持ちで私と話してるの?」
感情が溢れ出して止まらない。
私、熱くなりすぎてる。
「毎朝の挨拶とか、話しかけてくれるのとか…
嬉しいよ?嬉しいけど…
どういうことなの??友情?同情?
それとも…」
言いかけで、風がものすごい強さで吹いて。
舞い上がったカーテンが私たちを隠した。
その瞬間だった………-----