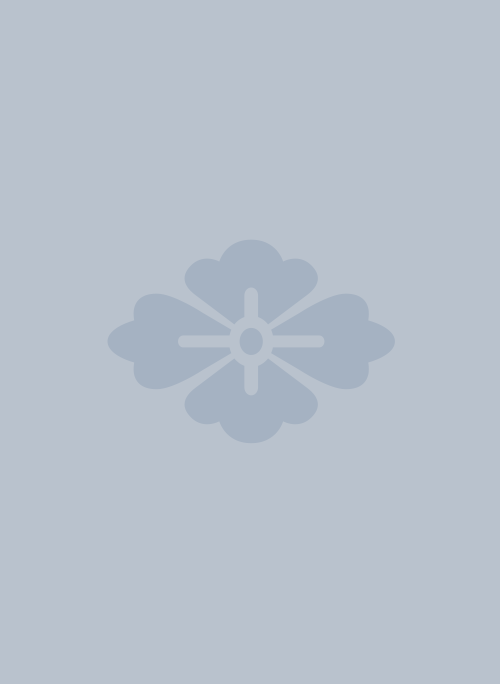数日後、竜一と一緒に温室に来た人に私は目を疑った。
「マツ...どうして?」
目の前に立っている人はマツ。
竜一ととても親しくしている様子に私は驚きを隠すことが出来なかった。
「そうだったな、知り合いだったんだな。」
そう言ってニヤリと笑う竜一。
その姿は私の神経を逆なでするには充分だった。
「竜一に何も聞いてない。お前には何も話す事はない。」
言い終わると同時に私は竜一に殴られ弾き飛ばされていた。
それでも私が視線を向けるのはマツ。
ねぇマツ、どうして竜一なんかと一緒にいるの?
旦那様死んじゃったんだよ。
彰人さんたちは警察に連れて行かれちゃったんだよ。
声にならない言葉が心の中で渦を巻くように暴れまくっていた。
「この女は俺とは何のかかわりもない。俺はお前に雇われてここにいたスパイなんだからな。」
私の目を見ながらマツの口から出た言葉に私は目を見開いたまま動けなかった。
マツが竜一の部下?
彰人さんと友達で、旦那様を助けるためにいるんじゃなかったの?
「嘘...嘘でしょう?マツ....。」
縋り付くようにマツの胸元のシャツに手を掛ける私をマツは迷惑そうに払いのけてモニターの前に足を進めた。