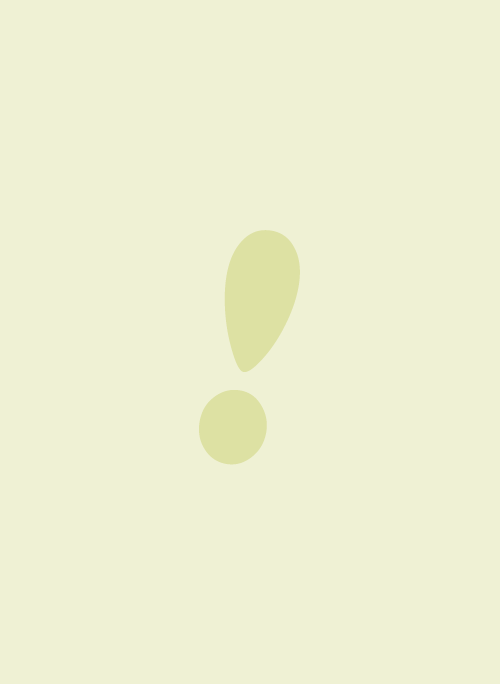部屋は薄暗く、もう日も暮れる頃だった。
青みがかった髪を重たそうに持ち上げ、その青白い顔肌を同じ色の手が触れた。
深い朱色の瞳が拒むように薄く開くと、そこはいつの間にか眠ってしまったであろう机の上だった。
その風貌の持ち主、ブラドが嫌々足を動かし向かったのは玄関だ。
黒いブーツの踵を鳴らし、外へ赴くと、空にはちらほらと星が瞬きつつある。
「良い天気だね、まぁ。厭味のように良い天気だよ。」
不機嫌そうに動かした唇に、聞いた者はなんと答えるだろう。
そのまま入りたての夜に溶け込んでいった。
青みがかった髪を重たそうに持ち上げ、その青白い顔肌を同じ色の手が触れた。
深い朱色の瞳が拒むように薄く開くと、そこはいつの間にか眠ってしまったであろう机の上だった。
その風貌の持ち主、ブラドが嫌々足を動かし向かったのは玄関だ。
黒いブーツの踵を鳴らし、外へ赴くと、空にはちらほらと星が瞬きつつある。
「良い天気だね、まぁ。厭味のように良い天気だよ。」
不機嫌そうに動かした唇に、聞いた者はなんと答えるだろう。
そのまま入りたての夜に溶け込んでいった。