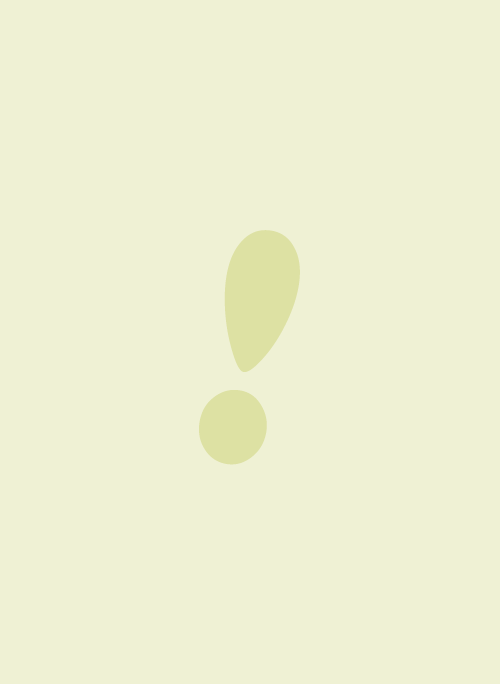俺は窓に掛かるカーテンを指先で少しだけ開き、その隙間から、ちらっと向かいの路地に目をやった。
今日は刑事がいないようだ…
ここ数日、組事務所と俺のアパートには、しつこい程毎日のように警察が張り込んでいた。
毎日同じ場所に同じクラウンが止まっているので容易に想像がつく。
張り込みがない事を見計らった俺は、ホッと胸を撫で下ろすと、素早くワイシャツに袖を通し、降ろし立てのスーツを身に纏った。
短い髪の毛をハードワックスで無造作に立てると、誰にも気付かれないようにアパートを後にする。
梅雨の明けた夏空が澄み渡り、階段を降りる俺の足取りも久しぶりに軽やかに感じる。
今日はリサと会う。
この歳になって、たかだかデートってだけで浮かれている自分の姿は、きっと周りから見たらさぞ滑稽に映るだろう。
普段何人もの女と身体を交わしていた俺は、『女というのは心よりも身体を癒す存在』だと割り切っていた。
それだけに、会えるというだけでこんなにも浮足立つ感情は自分自身でも不思議だった。