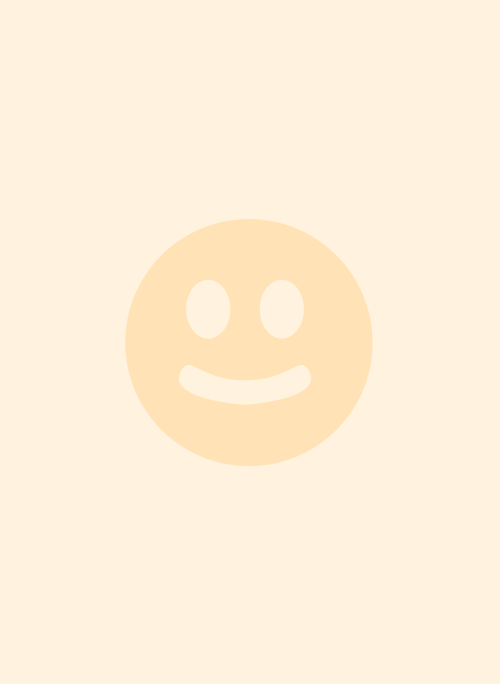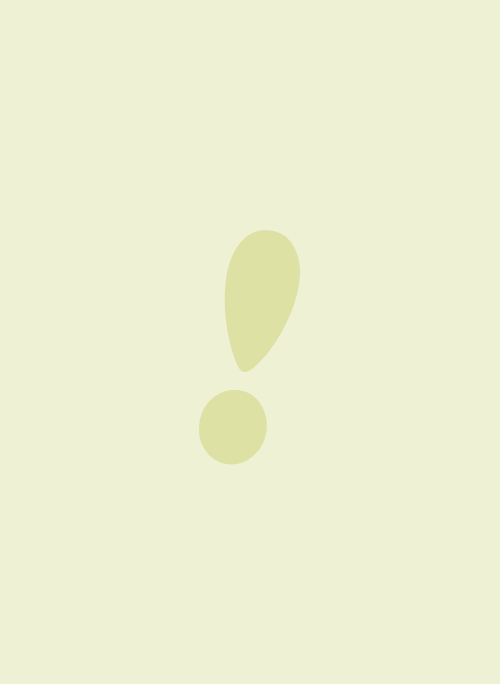そう言ってタツヤは前歯の抜けた口を大きく開けて笑った。
確かに江藤会では幹部の人間しか潤ってはいない。
俺たちが必死の思いで毎月上げるシノギの殆どは組に上納する。
しかもシュウイチさんは江藤会の中でもケチな事で有名だ。
この前振る舞ってくれた飲み代の50万円は奇跡に近い。
「タツヤ…お前今月のシノギはどうなんだ?」
「ん?…ああ、100万円上がればいい方かな?」
「はあ?まじかよ…!?」
俺は驚きのあまり声を荒げた。
「この不景気だからな…テキ屋はもうダメだ。
組に入れたら俺や弟分達の取り分は殆ど残らねえよ」
タツヤがやっているテキ屋は祭りの多い夏が稼ぎ時だ。
今月は至る所で祭りがあってるというのに…
「俺ってこの仕事向いてねえのかもしれねえな…
就活でも始めっかなあ…」
そう言いながら、広間から出て行くタツヤの後ろ姿はどことなく悲しげだった。