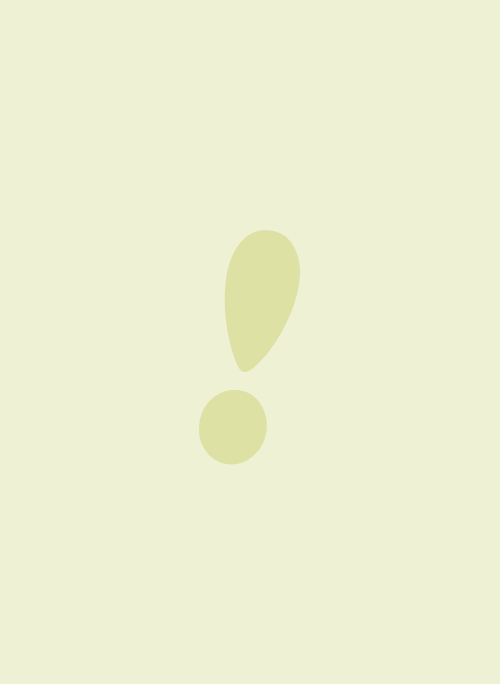お昼と同じように、壁際の席に案内された。
立てかけられたらメニュー表を見ることもなく、ドリンクバーを3つ注文した。
メロンソーダの気泡がストローにくっついているのをただ見つめていると、マサキさんが口を開いた。
「ん?どうしたのかな?俺になにか用があったんだよね?」
マサキさんをちらっと見ると、氷がたくさん入ったアイスコーヒーを飲みながら、あたしに笑いかけていた。
…あたしは、なにも言えなかった。
なにから訊いていいのか、
どう訊いていいのか…
あたしの頭の中は混乱したままだった。
.:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:.