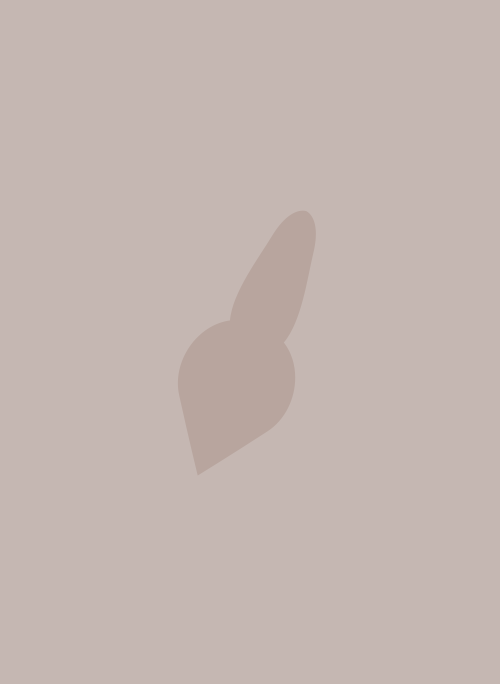彼女は伴侶となるその男の腕をとり、小さくほほ笑んで神父に向き合った。
神父の低い声が、僕にはまるで御経を読む坊主の声に聞こえた。
そして、それに混じって彼女のはっきりした澄んだ迷いのない声を聞くと、また涙がこぼれそうだった。
彼女の細い指にプラチナ色に輝く小さなリングがゆっくりとはめられていく。
それを複雑な想いで見送る。
あの手をとって、あのリングをはめるのが自分であったなら、どんなに幸せだったろう。
そしてそんな日をずっと思い描いてきたこのどうしようもない苦い、苦い想いは一体どうしたら良いのだろう?
ぶつける場所のない想いが、小さな黒煙をあげてじりじりと燃える。
神父の低い声が、僕にはまるで御経を読む坊主の声に聞こえた。
そして、それに混じって彼女のはっきりした澄んだ迷いのない声を聞くと、また涙がこぼれそうだった。
彼女の細い指にプラチナ色に輝く小さなリングがゆっくりとはめられていく。
それを複雑な想いで見送る。
あの手をとって、あのリングをはめるのが自分であったなら、どんなに幸せだったろう。
そしてそんな日をずっと思い描いてきたこのどうしようもない苦い、苦い想いは一体どうしたら良いのだろう?
ぶつける場所のない想いが、小さな黒煙をあげてじりじりと燃える。