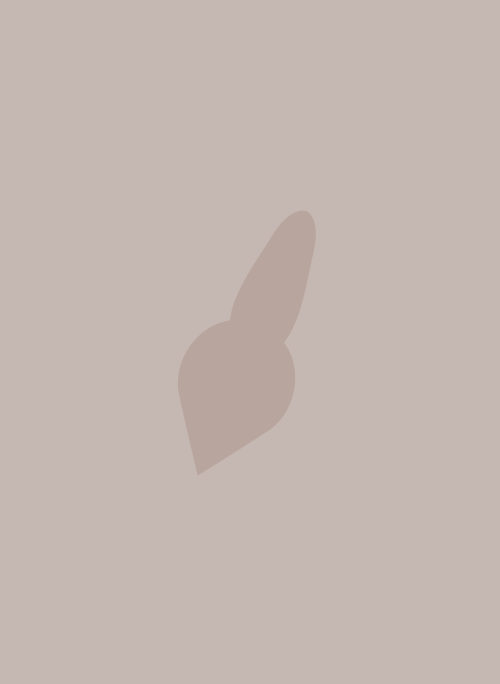「零、頼みがある」
旦那様に呼ばれ、"頼み"という単語にクエスチョンマークを飛ばしながらも、俺はなんでしょうかと返事をした。
「優姫の専属執事になってくれ。お前は、優姫とだいぶ年も近い。…頼まれてくれるか?」
旦那様は、たくさんの人間に対し、お優しい感情を持っていらっしゃる。
今だって、ただの執事である俺に拒否権はないのに、そのように仰ってくださる。
なんと、立派なお方なのだろうか。
「喜んで」
俺は微笑んでそう言った。
それに対し、旦那様はしっかりとしたお声で「頼む」と仰られた。
「優姫様」
「…はい」
「これから、お世話をさせていただきます、垣元 零でございます。未熟者ですが、よろしくお願い致します」
優姫様に向き直り、右手を左胸に当てて会釈すると、彼女はたどたどしく、「よろしくお願いします」と言葉を放った。
真っ白な光が俺たちを包み込んだ頃、桜の花びらがヒラリと一枚だけ舞いあがった。
旦那様に呼ばれ、"頼み"という単語にクエスチョンマークを飛ばしながらも、俺はなんでしょうかと返事をした。
「優姫の専属執事になってくれ。お前は、優姫とだいぶ年も近い。…頼まれてくれるか?」
旦那様は、たくさんの人間に対し、お優しい感情を持っていらっしゃる。
今だって、ただの執事である俺に拒否権はないのに、そのように仰ってくださる。
なんと、立派なお方なのだろうか。
「喜んで」
俺は微笑んでそう言った。
それに対し、旦那様はしっかりとしたお声で「頼む」と仰られた。
「優姫様」
「…はい」
「これから、お世話をさせていただきます、垣元 零でございます。未熟者ですが、よろしくお願い致します」
優姫様に向き直り、右手を左胸に当てて会釈すると、彼女はたどたどしく、「よろしくお願いします」と言葉を放った。
真っ白な光が俺たちを包み込んだ頃、桜の花びらがヒラリと一枚だけ舞いあがった。