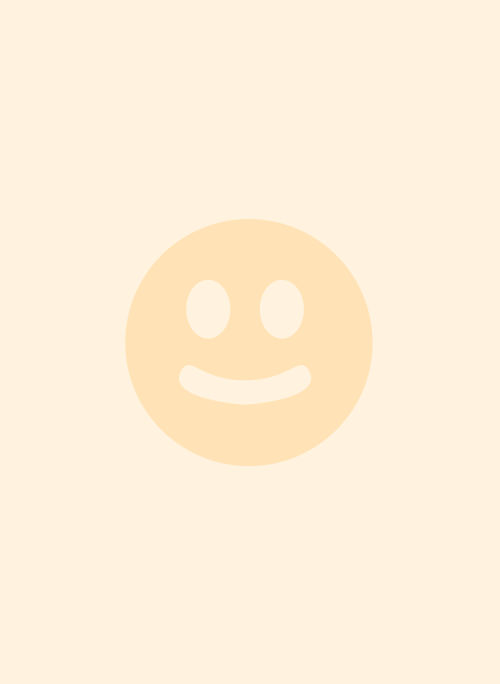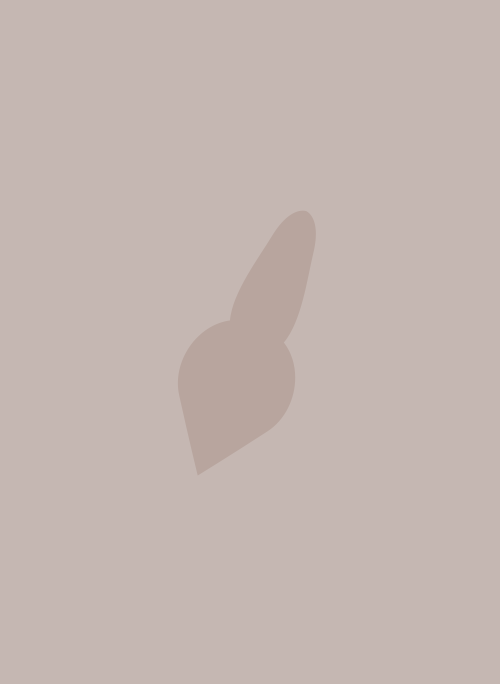「とりあえず…陽姫お姉ちゃんに会っていただけませんか?」
「あぁ…ありがとうございます、優姫さん」
白石さんは棺桶の傍まで行くと、死に化粧を施し寝ているように横たわるお姉ちゃんの手を握り、「陽姫…愛してるよ」と呟いた。
彼の肩が震えている。
泣いているのだと、その様子から伺えた。
お姉ちゃん…。
泣いてくれる人が、貴女にはいるのですね。
貴女の死を嘆いてくれる人がいる貴女は、なんて幸せ者なんでしょうか。
私は…泣けない。
貴女が悲しむだろうから、私だけは泣けない。
「お姉さんが亡くなったというのに…」
「涙ひとつ見せないなんて」
「なんて冷たい…」
周りの人達の声が、胸の脆い部分を攻撃する。
もうそこは、音をたてて崩れていきそうなのに。
それでも、言葉は棘となり凶器となり私の心を容赦なく攻撃する。
痛い。
「――失礼する」
すると、どっしりと安定した低い声が、そこらじゅうに響いた。
そして私の前まで来ると、50代くらいのその人は言った。
「優姫…だね?」
「……はい」
何故私の名前を知っているんだろうと疑問にも思ったが、彼のその声と姿は私に懐かしさを与えていて、少しだけ戸惑った。
「あぁ…ありがとうございます、優姫さん」
白石さんは棺桶の傍まで行くと、死に化粧を施し寝ているように横たわるお姉ちゃんの手を握り、「陽姫…愛してるよ」と呟いた。
彼の肩が震えている。
泣いているのだと、その様子から伺えた。
お姉ちゃん…。
泣いてくれる人が、貴女にはいるのですね。
貴女の死を嘆いてくれる人がいる貴女は、なんて幸せ者なんでしょうか。
私は…泣けない。
貴女が悲しむだろうから、私だけは泣けない。
「お姉さんが亡くなったというのに…」
「涙ひとつ見せないなんて」
「なんて冷たい…」
周りの人達の声が、胸の脆い部分を攻撃する。
もうそこは、音をたてて崩れていきそうなのに。
それでも、言葉は棘となり凶器となり私の心を容赦なく攻撃する。
痛い。
「――失礼する」
すると、どっしりと安定した低い声が、そこらじゅうに響いた。
そして私の前まで来ると、50代くらいのその人は言った。
「優姫…だね?」
「……はい」
何故私の名前を知っているんだろうと疑問にも思ったが、彼のその声と姿は私に懐かしさを与えていて、少しだけ戸惑った。