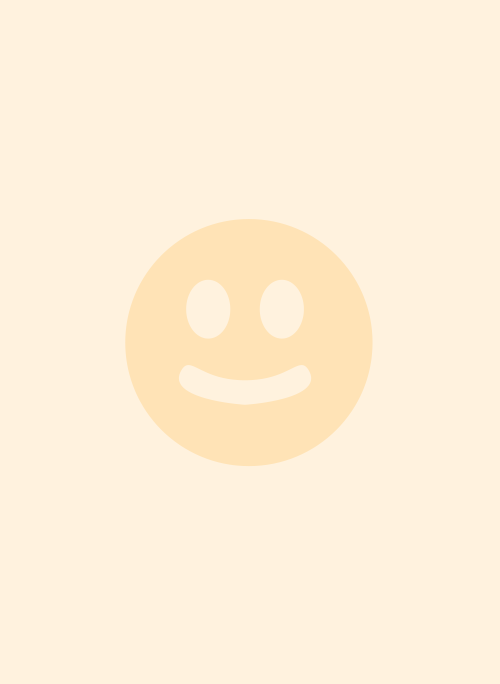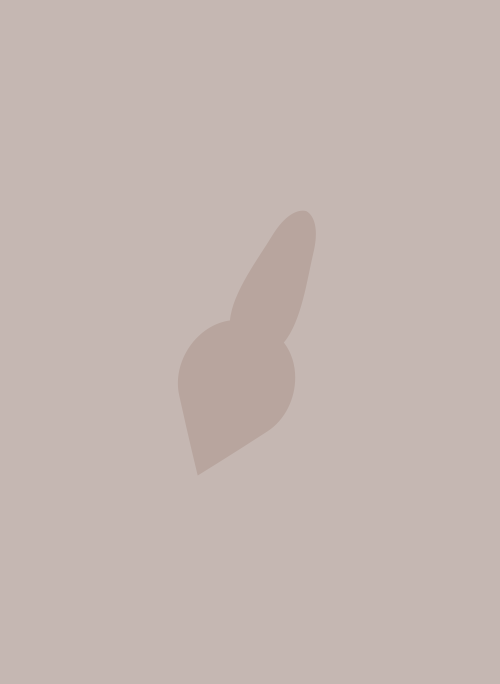痛みに怯え、暗闇の冷たさに震える彼女に手も差し伸べられない弱虫だった。
それでも彼女の傍にいるのはきっと、冬真様からのご命令だからという理由だけではない。
俺は、彼女の光になりたいんだ。
冬真様が俺の光になってくださったように、希望になってくださったように。
「優姫様、おやすみなさいませ」
サラサラと流れる彼女の髪を撫でる。
願わくば、貴方様が苦しい夢を見ませんように。
そして俺は、彼女の部屋を後にした。
「明日…天気が良ければ外でお茶でもするか……」
銀色の月が、ほんの少しだけ笑っていた気がした。
それでも彼女の傍にいるのはきっと、冬真様からのご命令だからという理由だけではない。
俺は、彼女の光になりたいんだ。
冬真様が俺の光になってくださったように、希望になってくださったように。
「優姫様、おやすみなさいませ」
サラサラと流れる彼女の髪を撫でる。
願わくば、貴方様が苦しい夢を見ませんように。
そして俺は、彼女の部屋を後にした。
「明日…天気が良ければ外でお茶でもするか……」
銀色の月が、ほんの少しだけ笑っていた気がした。